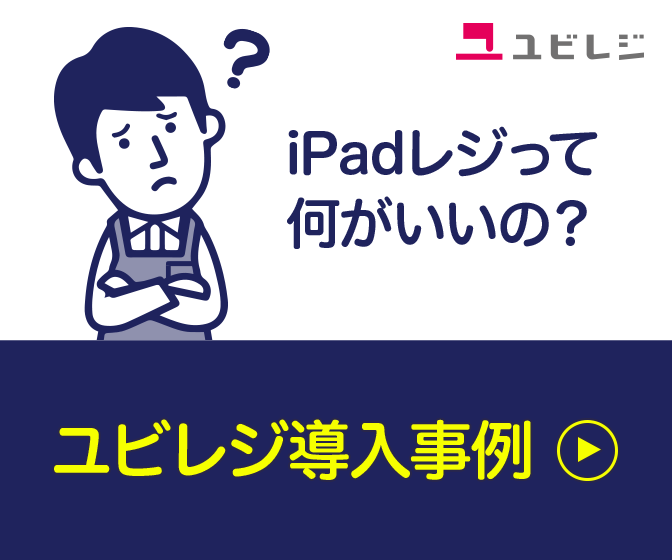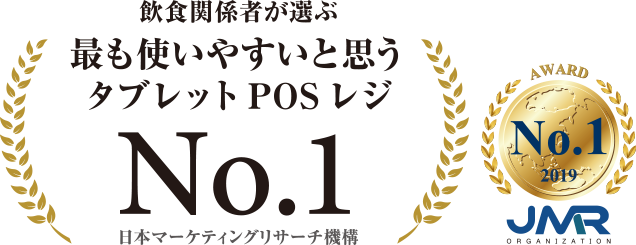飲食店を経営していると、会計時によく言われるのが「領収書ください」という言葉ではないでしょうか。そのような領収書ですが、皆さんは、領収書には正しい書き方があることをご存知でしょうか。実は何となく書いている……という方も中にはいらっしゃるかもしれません。
しかし、領収書の書き方に不備があると、渡したお客様が経理処理をする時に困ったり、場合によっては知らない間に脱税行為をしていることになったりするのです。
そこで今回は、領収書の正しい書き方についてご紹介いたしますので、しっかり実践しましょう。
領収書とは

領収書の役割とは?
領収書とは何のために発行するのでしょうか。また、領収書を必要としている人とはどのような人なのでしょうか。
まず領収書とは、自分が金銭を確かに受け取ったという証明書です。飲食店でもらった領収書を会社に提出することで、それは「確かに支払った」という証明になり、二重請求や過払いなどのトラブル防止にもなります。
会社の規定にもよりますが、その飲食代を「仕事上必要な食事代」と認められれば、会社から支払ってもらえます。その飲食代が「個人的な飲み食い」だと判断されれば、支払われない場合もあるでしょう。
会社はその領収書を証憑書類として、使ったお金を必要経費として利益から差し引き、税務署に申告して納税額を少なくします。個人事業主の場合も同様に、もらった領収書を証憑書類にして、確定申告で納税額を少なくします。
つまり、「領収書」は会社に対する「仕事上必要な飲食代を払った」証明となります。会社や個人事業主にとっては、税務署に対して必要経費の証明になるものなのです。
そういう意味では、飲食店経営者の方の場合も、店舗で使うための物品を購入した場合などは領収書をもらい、税金の申告時に必要経費の証明にしているはずです。
発行する義務はある?
民法では「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。受領した者=買い手が売り手に対して領収書の発行を請求することが可能です。したがって、買い手が要求すれば、売り手は領収書を発行する義務が発生することになります。
引用:民法第486条【受取証書の交付請求】 改正の概要 | 法務省
「領収書」と「領収証」どちらが正しいのか
税金関係の書類を読んでいると、その中に領収「書」という言葉が出てきたり、領収「証」という言葉が出てきたりして、いったいどちらが正しいのだろうと戸惑うかもしれません。
実は、「領収書」と「領収証」との間には明確な違いはありません。厳密に言えば、「領収証」は金銭授受が発生した時に、受け取った側がその事実を証明するために発行する書類のことで、役所や金融機関はこの言葉を使います。
一方、「領収書」はお金だけではなく商品も含めた受取りの事実を証明するために発行する書類のことで、一般のお店や企業がこの言葉を使う場合が多いでしょう。
実際にはどちらも混同して使われていますので、あまり気にする必要はないでしょう。
領収書とレシートの違い
法律上、レシートは領収書同様、商品の代金、サービスの対価を支払った事の証明として認められており、国税庁のホームページに以下の記述があります。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
領収書は手書きで手間もかかるため、レシートより正式な証明書となるようなイメージがあるかもしれませ。しかし領収書の場合、購入した商品を「品代」として記入することもあり、その点では購入品目の明細が記載されているレシートの方が経理上でも分かりやすく、信頼性が高いとも言えます。万が一税務調査が入った場合にも説明が容易になります。
ただし、会社によっては一定金額以上は領収書がないと経費精算しないというルールを設けている場合もあり、捉え方はそれぞれの会社によって変わってくるようです。
領収書の保存期間はどのくらい?
法人の場合
法人での領収書保管期間は7年間と決められています。この期間の起算は、領収書の発行日から7年間ではなく、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。間違えないよう注意してください。
引用:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
個人事業主の場合
白色申告と青色申告とでは保存機期間が異なります。
白色申告の場合・・5年間
青色申告の場合・・・7年間 ※前々年分所得が300万円以下は5年
電子データでの保存も可能
電子帳簿保存法の成立後も、法人や個人事業主は領収書を7年間保存しておかなければならないとされていました。しかし、ペーパーレス化が一層推進される中で、一定の条件を満たすキャッシュレス決済であれば領収書原本の保存は不要となりました。
詳細をこちらの記事で解説していますので、ご確認ください。
【おすすめ関連記事】
経営の効率アップにもつながる!電子帳簿保存法の導入メリットと適用条件を抑えよう
領収書を正しく書く理由とは

領収書を間違いなく正確に記入することがなぜ重要かというと、内容に不備があったり間違ったりしている場合、領収書が無効と判断され税務署がそのお金を必要経費だと認めてくれない可能性があるからです。そうなってしまうと、会社や個人事業主は税金を多く支払わなければなりません。
したがって、会社としては社員が飲食店の領収書を持ってきた時に、その代金をまず税務署が認めてくれるかどうかという観点でチェックし、そこで合格しなければその代金を支給してくれません。つまり、領収書が受理されなければ、飲食代は個人負担になってしまいます。
こういったことから、税務署が認めてくれる正しい領収書を発行しなければ、お客様に損をさせてしまう可能性があるのです。
また、中には「日付を空白にしてほしい」などと要求してきたリ、さらにひどい場合は「記載金額は白紙でちょうだい」という場合もあるかもしれません。これは、本来は個人の飲食代なのに、取引先などと飲食をしたように見せかけるために、スケジュール上矛盾がない日付の領収書にしようとしたり、あるいは、本当に使った代金より水増しをして会社に請求し、その差額を儲けようとしたりすることが目的とされます。
そのため、このような要求は悪事の手助けをすることになりますので、お断りしましょう。たとえば、実際の支払額に1万円を上乗せして書いてあげたりした場合は、最悪のケースでは私文書偽造、あるいは詐欺罪のほう助として、飲食店側が訴えられる可能性もあります。訴訟問題に発展しないよう、最大限の注意が必要です。
領収書の正しい書き方

【領収書サンプル】

1.通し番号
通し番号の記載は義務ではありませんが、発行先からの問い合わせの際に照合作業がスムーズに行えたり、架空請求などの不正の抑止にもつながるため通番での管理を行っておいた方が良いでしょう。
2.発行日
日付は、飲食代を受け取った日付を記載します。注意して頂きたいのは、「飲食をした日」ではなく「代金を受け取った日」です。たとえばツケの場合、ツケの元となった飲食の日ではなく、後日ツケを支払ってもらった日の日付で発行するのが正しい書き方です。
また、日付を空欄にしたり、実際と違う日付で書くことは、非常に悪く言えば詐欺罪の片棒を担ぐことになりますから、絶対にやめましょう。
3.宛名
宛名は正式名称で書きます。株式会社であれば「株式会社●●」「●●株式会社」です。「(株)」という書き方はNGです。
「上様」も基本的にはNGとなります。中には、「宛名はお客様の方で」と気を利かしたつもりで渡す飲食店もありますが、それもNGです。なぜなら、業務上必要な経費かどうかがそれでは判断できないからです。
4.金額
支払った代金を上乗せしたり、架空の飲食代を支払ったことにして税金を安くしたりして会社からお金をだまし取ることを防ぐために、領収書の金額欄は、あとから改ざんできないように書くことが基本です。
具体的には
金額の数字の頭に「¥」マーク、または「金」と書く
金額の数字の最後に「-(ダッシュ)」マーク、または「也」と書く
金額は三桁ごとに「,(カンマ)」をつける
ということによって、改ざんを防ぎます。
飲食店ではあまり多くはありませんが、金額が十万円、百万円という大きな単位になる場合は
「1」万円」のかわりに「壱」
「2」は「弐」
「3」は「参」
「5は「伍」
「十」「10」は「拾」
「万円」のかわりに「萬円」
と書いたほうが、より領収書の信頼性が高まります。
また、金額は基本的に税込みで記入します。お客様から税抜金額で書いてといわれた場合は、消費税分を但し書き欄に書きます。
5.但し書き
決まった書式の領収書の場合、金額欄の下に「但し」という記載があります。ここに書く内容を、「但し書き」と言います。
但し書きとは、その費用が本当に必要経費になるかどうかを証明するものです。たとえば、焼き鳥屋でお客様が家で食べるために持ち帰りをした焼き鳥の領収書を、「品代として」ではなく「飲食代として」と書いてしまうと、その領収書はその店で飲食をしたことを証明するウソの領収書になってしまいます。ですから、但し書き欄も正しく書く必要があるのです。
また、仮に本当に正しく使った必要経費の場合でも、会社の経理担当者は但し書きを見て、その経費が「接待費」なのか「福利厚生費」なのかなどと判断します。重要な判断材料としても、正しく書く必要があるのです。
ただし、飲食店の場合の但し書きはそれほど種類がありませんので、
お食事代として
飲み物代として
お品代として(持ち帰りなどの場合)
の3つ程度で対応できるでしょう。
6.収入印紙
5万円以上の代金の領収書に印紙を貼る必要があり、記載された受取金額により印紙税額に違いがあります。
税額5万円以上100万円以下は200円、100万円以上200万円以下は400円です。なお、5万円以上の領収書で収入印紙が貼付されていないものは正式な領収書として認められません。お客様が接待交際費などの経費として落とせなくなるので、常にお店には収入印紙を用意しておきましょう。
貼り付けた印紙には必ず消印を押さなければいけません。押印をする人は、領収書に氏名が記載されている飲食店に関わる人や代理人である必要があります。また、彩文(収入印紙の縁の部分)と課税に関する文書にまたがるように押印しなければならないので覚えておきましょう。
7.内訳
税別の本体価格と消費税額を分けて記載します。
④の金額の書き方と同様に、改ざん防止のため、金額の頭に「¥」マーク、または「金」と書く。
金額の最後に「-(ダッシュ)」マーク、または「也」と書く。
金額は三桁ごとに「,(カンマ)」をつける。
8.発行者
領収書の発行元の連絡先情報、店名(会社名)、住所、電話番号を省略せず正しく記載します。店判や社判は必須ではありませんが押印するのが一般的です。
インボイス制度の導入により記載項目が追加に
2023年(令和5年)10月1日よりインボイス制度が導入されます。これは2019年10月の消費税10%引き上げを受けての改正で、複雑になった消費税を正確に把握する目的で導入される制度です。仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税控除)を受けるための請求書や納品書の要件や関連する手続きが必要になります。これに伴い領収書の記載にも以下の①〜⑤項目追加が必要になります。
小売業、飲食店業、サービス業等の不特定多数の者に対して販売等を行う取引については、適格請求書の代わりにレシートが適格簡易請求書として該当します。軽減税率が適用される場合に税区分の記載が必要であるため、下記に該当する事業主はレシートの見直しを検討してください。
- 飲食品や日用品など販売する商品が多数あり、税率が複数混在している
- 経費としてレシートの発行が求められることが多い
- 取引先にインボイスを請求する法人企業が多い

記入を間違えた場合の訂正方法
記入を間違えた場合、基本的には新しく書き直しましょう。間違えた領収書は破棄するのではなく、書き損じとわかるように大きく×を書き、複写とともに保管しておきましょう。
やむ終えない事情により訂正が必要な場合、該当箇所に二重線を引き訂正印を押して余白に正しい情報を記載します。修正テープ、修正液での訂正は認められませんので注意してください。
領収書には収入印紙が必要

領収書の「正しい書き方」は、お客様や領収書の請求先となる会社にとって必要な「正しさ」となります。しかし、領領収書の「正しい書き方」は、お客様や領収書の請求先となる会社にとって必要な「正しさ」となります。しかし、領収書は飲食店側にとっても大切な「正しい書き方」があります。飲食店が正しい書き方をしていなければ、国税庁から「脱税」だとみなされてしまうので注意が必要です。では、飲食店が注意しなければならないのは何か。それは、「収入印紙」の問題です。
収入印紙が必要な理由
収入印紙は、領収書の隅に貼る「切手」のようなものです。収入印紙は店側が前もって購入しておき、飲食代などの支払額に応じて領収書に貼らなければなりません。
その理由は、一定額以上の収入が店側にあって、それを証明する書類である領収書を発行した場合、「払った・払わない」のトラブルが生じて裁判などになった際の証拠書類になるからです。つまり、訴訟の際には国が領収書を受け取った事実、支払った事実を証明してくれることになります。国への「証明代」として国に納めるのが「印紙税」です。実は、収入印紙を買うということは、それ自体が国に税金を納めていることなのです。正しい言い方をすれば、収入印紙は「買っている」のではなく、「印紙税」を払った証明として発行してもらっているのです。
貼らない場合罰金も
法律で定められた規定に沿って収入印紙を貼らない、つまりは印紙税を払っていないということはすなわち脱税になります。支払っていない事実が税務署に指摘された場合は、罰金を含めた税金を国に納めなければなりません。
印紙税法という法律の中では、「収入印紙を貼らなかった場合は、払うべき印紙税のほかに、収入印紙の額面の3倍の金額を過怠税として支払わなくてはいけない」と定められています。つまり、たった200円の収入印紙をごまかしただけで、800円の税金がかかるのです。
それが1件だけであれば少額で済むでしょう。しかし、慢性的に印紙税を支払っていないのであればすべてさかのぼって調査され、最悪の場合何万円、何十万円と税金を納めなければならないこともあり得ます。
ですから、規定に基づいて必ず収入印紙は貼ることが大切であり、経営者の義務でもあります。
収入印紙はいつ貼ればいいの?
では、どのような場合に収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。原則としては1回の受取額が5万円以上の領収書を発行する場合からとされています。5万円未満の場合は非課税となるため不要です。あとは、受取額に応じた以下の額面で決まってきます。細かく言うと、領収書に記載する金額が税込みの場合は税込5万円以上で印紙を貼ります。消費税が別に記載してあり、金額欄が税抜きの場合は税抜き5万円以上で貼ります。受取額に応じた収入印紙の金額を下記に記載しておきますので、ご確認ください。
| 記載された受取金額 | 収入印紙金額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
|
受取金額の記載のないもの (非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |
200円 |
引用:第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表|国税庁
収入印紙には割印が必要
収入印紙を貼ったら、「割印」が必要です。これは、収入印紙を受け取った人が上手く剥がして流用することを防ぐためのものです。割印の方法は、収入印紙と領収書をまたいで店長などの印鑑を押すか、あるいはサインをすることになります。
クレジットカード払いの領収書の書き方

ここまでご紹介した内容は、「現金で」支払っていただいた場合の領収書の書き方です。では、現金での支払方法と並ここまでご紹介した内容は、「現金で」支払っていただいた場合の領収書の書き方です。では、現金での支払方法と並んで多いのとされるクレジットカードでの支払いの場合はどうなるのでしょうか。クレジットカード利用の場合、領収書の扱いが現金とは異なりますので注意が必要です。
クレジットカードの場合は領収書発行の義務はない?
厳密に言うと、クレジットカードで支払っていただいた場合、店舗はお金を受け取っていません。つまり、後日クレジットカード会社から支払うということをお客様から一種の「ツケ払い」として言われているので、店側としては店舗が契約しているきちんとしたクレジットカード会社ならと信用し、「ツケ払い」を了承したということになるのです。つまり、クレジットカードとは「信用取引」です。
領収書は先ほどご説明したように「代金を受領した証明」ですから、クレジットカードで「支払った」といっても、実は「受け取ってはいない」のです。本当の受け取りは、クレジットカード会社からの入金があった時点です。
ですから、本来的にはクレジットカードでの支払いの場合、店側としてはその代金に対する領収書の発行義務はありません。その代わりに、お客様には「カード控え」という形で、クレジット伝票をお渡しすることで、お客様側に支払いの管理をしてもらうことになります。
領収書がほしいと言われたら?
クレジットカードで支払われたお客様の中には、どうしても領収書が欲しいという方も多いはずです。この場合、発行は法的に「禁止」されているわけではありませんから、発行するかどうかは店側の判断に委ねられています。したがって、発行しても問題はありません。
ただし、その場合は領収書の但し書き欄に必ず「クレジットカードにてお支払い」と記載しましょう。それによって、この書類は法的な領収書ではないという証明になります。
クレジットカード払いの場合は収入印紙は不要?
「クレジットカードにてお支払い」という但し書きがなぜ重要かというと、この言葉を書くことで、その書類は税法上の「領収書」ではないということの証明になるからです。これにより、たとえ5万円以上の金額であっても、収入印紙を貼る必要がなくなります。
クレジットカード払いであったにも関わらず、その旨を但し書きに明記しない場合は、その書類は「領収書」になってしまいます。よって、5万円以上の場合には収入印紙を貼らなくてはなりません。
これらの点を考慮に入れ、クレジットカード支払いの場合には十分に注意しましょう。
まとめ

いかがでしょうか?
何気なく書いていた領収書も、実はそれぞれの項目に意味があり、正しい書き方があるのです。これを守らないとお客様に何気なく書いていた領収書も、実はそれぞれの項目に意味があり、正しい書き方があるのです。これを守らないとお客様に迷惑をかける場合も、店舗が損害を受ける場合もありますので、領収書について十分理解をして正しく実行しましょう。