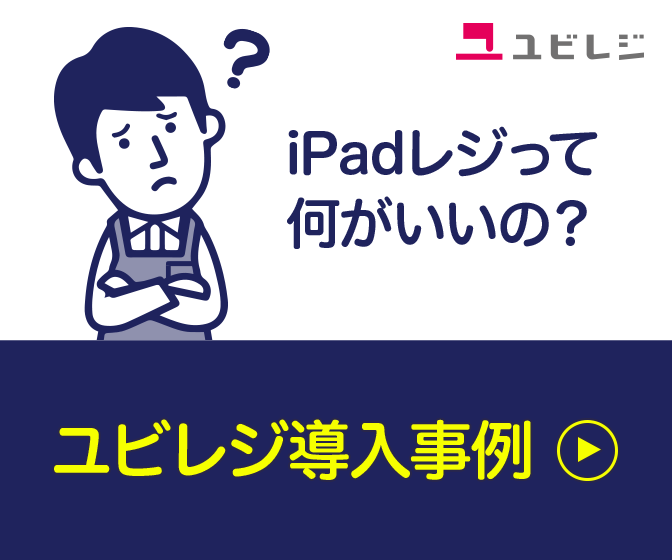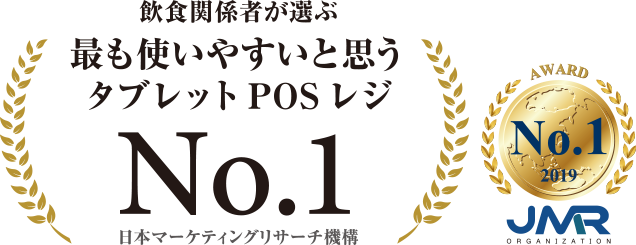消費税が8%から10%に引き上げられる予定となっていますが、同時に酒と外食を除く食料品に軽減税率の導入が決まりました。
軽減税率は大きな影響が予想されますが、その中でも軽減税率が適用されない外食産業は対策が必須でしょう。特に以下の2点は必ず確認して、必要があれば対策を実施しましょう(詳しくは後述します)。
- お店は軽減税率が適用される形態なのか?
- レジと経理は複数の税率に対応できる体制か?
今回は、飲食店経営者が軽減税率について知っておくべきことと、どう対応すればいいのかを説明します。

軽減税率とその目的、適用範囲は?
そもそも軽減税率とは、その名のとおり税率を標準税率から軽減することです。
今回の例でいえば、食料品は生活の根幹であるので、その負担を抑えるために税率を8%に据え置くことが決められました。ただし、適用範囲は酒と外食を除く食料品のため、外食産業の客離れが懸念されています。景気動向によっては、店舗運営に大きなダメージを与える可能性もあります。
また、同じ商品でもテイクアウトは8%だが店内では10%、出前は8%といった外食の線引きがわかりづらいという指摘もあります。このように、まだ議論が詰め切れてはいませんが、いまの時点で飲食界に予想される状況とその対策を説明します。
外食産業にとっては正念場?
飲食業界は外食産業以外にもコンビニの商品ラインナップの豊富な品揃えや外国から新しいお店が参入してきたりと、日々激しさを増しています。
その中で税率の差がついてしまうと、お客様がどうしても外食を遠ざける傾向が出ると予想されます。そのため、もし自分のお店は軽減税率が適用されないならば、何らかの対策を立てなければなりません。
そして軽減税率と標準税率が混在しているならば、複数の税率に対応する経理体制を整える必要もあります。なお、政府は複数税率に対応するレジ、パソコン、経理ソフト導入の助成金を検討していますが、やはり大事なのは体制と戦略づくりです。
戦略策定:お客様をどう呼び込むか
先にも述べたように、案としてすぐ思い浮かぶのが税率8%のテイクアウトサービスの導入です。
しかし、これは営業時間や容器購入、メニュー開発のコストの問題で現実的ではないかもしれません。
これからメニュー開発を行い、戦略を練るには個人経営ではなかなか厳しいでしょう。スケジュールに関しても、新たな取引業者の選定や発注フローの構築、従業員へのマニュアルの作成、研修など、時間以外のコストも発生します。
また、衛生面での保健所とのやり取りなども考えると経営者として対応が追い付かなくなり、既存の事業が回らなくなってしまします。
まずは、今あるものでどう戦っていくかを考えます。いかに、これまでと変わらない品数を提供していくかを検討しましょう。
戦略策定の具体例:商品の値上げと据え置きの方法/プランの細分化
具体的には、まず価格を上げる商品と据え置く商品を明確化します。特に、お店の売れ筋や、お客様の認識もある看板メニューに関しては据え置くことをおすすめします。
看板商品の値段は据え置きして、他のメニューの値上げを考えます。また、生ビールなどドリンクの売れ筋に関しても同様の考えを適用するといいでしょう。さらに、コース・プランとして単価を見せないようにしてお得感のあるものをつくってみてはどうでしょうか。こうすることによって、客数をある程度維持しながら売上を確保することが出来ます。
これまでの飲み放題プランやシーズンごとの忘年会プランだけでなく、シーンによって細分化したプランを作るといいでしょう。たとえば、
上記のようなプランであれば、料理のグラム数など通常の商品とは異なった分量での提供が可能ですし、お得感があるので顧客満足に関しても落ちることはありません。仕入れ先を変えたりする中での原価調整よりも圧倒的に工数がさけます。
体制づくり:専門家と相談を
複数の税率を扱う場合、税額控除の計算の複雑化、事務負担の増加が予想されます。経理担当者も、その経験値によっては対応ができないことも想定されます。
また、経理担当者がいないため経営者が兼務して行っているような規模の会社ではなおさらでしょう。
そのため、税理士や会計士にあらかじめ相談して、対応できる体制をつくっておきましょう。特に、今後複数の店舗の出店や、同じ飲食店でも違うコンセプトでメニューが異なるような店舗を出店予定なのであれば早々に検討すべきです。
軽減税率に関しては、すべての業界にとって大きなインパクトを与えるニュースとなっています。経理担当者がいるのであれば相談し、専門家との接点を持つことが求められます。早めの対策を心掛けて、体制を整えておきましょう。
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。