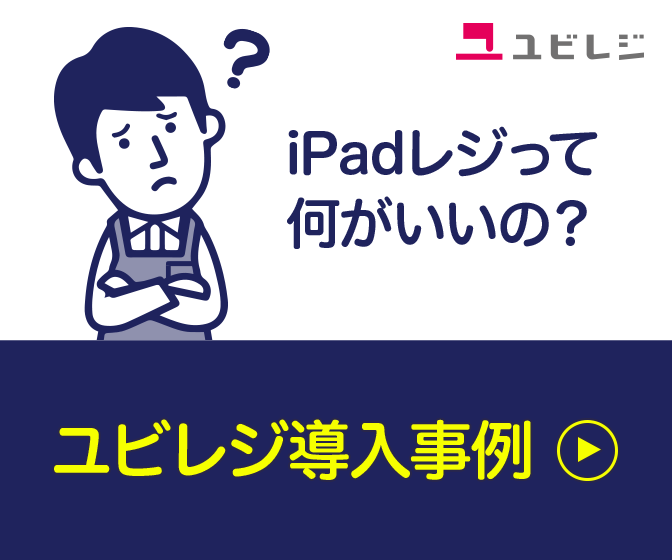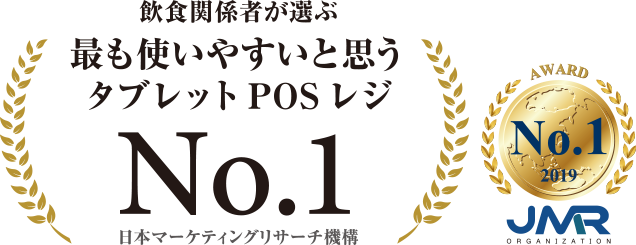この記事のもくじ

飲食店を経営するうえで発生する経費は、「固定費」と「変動費」に大別されます。この2つの合計を売上から差し引いた分が利益というわけです。利益が思うように出ないとすれば、売上か経費のどちらか、あるいは両方に問題があると考えなければなりません。
売上(入ってくるお金)を伸ばすのは容易なことではありませんが、経費(出ていくお金)は無駄をなくせば抑えることができるので、その分利益を増やすことができます。
そこで今回は、サービスの質を落とすことなく利益を上げるためのコストコントロールについて、考えてみましょう。
固定費とは?

売上の変動にかかわらず発生する費用のことです。業種によって分類のしかたは異なりますが、飲食店の場合は家賃、リース料、減価償却費、支払利息などが主なものです。
リースとは冷蔵冷凍庫のような高額な機器をリース会社が新品を購入し、それをお店が長期間賃借するシステムで、必要なときに借りてそのつど料金を支払うレンタルとは区別されています。
減価償却は、長期にわたって使用することが想定される設備や車などを、購入時点で全額を費用として計上するのではなく、使える年数(耐用年数)に応じて費用化するものです。
変動費とは?

売上の変動に合わせて金額が変わってくる費用のことで、主なものに原価、人件費、水道光熱費、宣伝広告費、消耗品費などがあります。
人件費は、月給制の社員の多い会社では固定費に分類される項目ですが、時給制で、シフトによって変わるアルバイトの賃金は変動費とするのが一般的です。
固定費と変動費の適性数値とは?

利益を確保するためには、経費を売上の90%以内に抑える必要があるといわれています。しかし、利益を出したいからと本当に必要な経費まで削減するのは、サービスの質の低下を招きかねないので要注意です。飲食店の場合、売上に対する経費の比率はそれぞれ以下のような数値が適正とされています。
固定費の適性値
- 家賃:7~10%
賃料、共益費などです。 - 諸費用:10%以下
減価償却費、支払利息、リース料などがこれにあたります。
固定費の合計は15~25%が適正比率となります。
変動費の適性値
- 原価:30~35%
売上高に対する原材料費の割合です。「売上高÷原材料費×100」で求める原価率で、これは利益を獲得するための指標となるものです(次項で詳述)。 - 人件費:27~30%
アルバイトの賃金、通勤交通費や食費、福利厚生費なども人件費に含みます。 - 水道光熱費:5~7%
ガス代、電気代、水道代。これは固定費に分類することが多いのですが、飲食店の場合は売上が伸びれば水道光熱費も上がるのが自然ですから、変動費とするのが一般的です。 - 広告宣伝費:3~5%
チラシ、ポスティング、フリーペーパー、ダイレクトメール、グルメサイトの掲載料などとなります。 - 消耗品その他:5%以下
事務用品、通信費、修繕費などがこれにあたります。
変動費は、合計60~70%が適正比率です。
以上の数値はあくまでも目安で、店舗の規模やコンセプト、立地条件などによって異なってきます。たとえば、ステーキを主力メニューとするレストランが良質の肉を仕入れようとすれば、原価は35%内には収まらず、40~50%になるかもしれません。それくらいの食材を使わないと顧客満足度を高めることができず、「安い肉を使う店」とマイナス評価されかねないので、数値にこだわりすぎないことも大切です。
では、適性数値を超えてしまう場合は、どのように調整すれば確実に利益を出すことができるのか、その方法についてご紹介します。
変動費をコントロールする方法とは?

利益を上げるには、「売上を伸ばして経費を抑える」が基本となります。しかし、売上は景気の好不況や天候、さらには競合店の出現などによって左右されるため、完璧に管理するのは困難です。それに対し、経費は不要なものは減らし、必要なものを増やすというように自分でコントロールすることができます。なかでも、飲食店の場合は変動費が経費の割合が大きいため、節約の意識を日頃から持つことにより費用をコントロールすることが求められます。
飲食店の変動費として大半を占めるのが、原価(原材料費)と人件費です。マーケット用語では、この2つを「FLコスト」といいます。FはFood(フード)で原材料費、LはLabor(レイバー)で人件費のことで、このFLの比率を60%に収めるのが望ましいとされています。
たとえば、売上が300万円だった場合、原材料費が150万円で人件費が100万円とすると、FLコストは「150万円 + 100万円 = 250万円」です。 FL比率は「250万円 ÷ 300万円 × 100 ≒ 83%」となり、60%を大きく超えてしまいます。このような場合は、原材料費か人件費を減らすなどして60%に収まるように調整する必要があります。どちらをどれだけ削減するかによって利益幅が変わってくるため、こうしたコストコントロールは経営の核ともいわれる重要な業務です。
人件費削減の例
先のレストランの例でいえば、お店の味を落とさないためには原材料費を減らさずに、人件費で調整することになります。
人件費を調整するというのは、スタッフの人数を減らすことではありません。スタッフが減ってしまってはサービスが行き届かなくなって売上増加どころではなくなりますから、人数を減らすのではなく、働く時間で調整することがポイントです。
具体的には、シフトを組む際に日々の売上を過去の売上を基に想定し、アルバイトの勤務時間はどれくらいが適切かを割り出します。適切な割り出しができれば、たとえば今まで6時間勤務だったアルバイトの勤務時間を1時間減らしても問題はないかもしれません。1時間勤務時間が減れば、1時間分の時給を減らすことも可能で、本当に必要な時間だけ働いてもらえるようになります。これは、スタッフにコスト意識を持たせるという点でも有意義な方法です。
原価削減の例
人件費を今以上に削れないという場合は、原材料費を削減することを考えます。それには、まず食材ロスをなくすことを徹底します。仕入れるときに何日ほどで使い切れるか、余った分はほかのメニューに回すことが可能かなどを考慮して発注する必要があります。
また、これまでの仕入れ業者とほかの業者を比較検討し、条件によっては業者を変更することも考えるべきでしょう。
このように、コストコントロールは決して簡単な業務ではありません。しかし、超優良店に分類されるお店では、原価率28%、人件費率22%に抑えているケースもあります。1%下げるだけでも、売上が300万円の場合3万円もの利益が増えることになります。1年続ければ36万円の利益増が見込めるのですから、コストコントロールの重要性がおわかりいただけたのではないでしょうか。
まとめ

いかがでしょうか?
お店を繁栄させるには、売上管理だけでなく経費の管理も毎日行うことが大切です。月末になって原価率が上昇していると分かっても、対処のしようがありません。売上に対して原価率がどの程度を占めているかを把握し、仕入を減らすなどの手を打つことがコストコントロールなのですから、毎日原価率を把握しておくことが必要です。
経営者や店長にとって、コストコントロールは最も重要な業務とされていますが、毎日のこととなるとかなりハードな作業となります。忙しくて十分な時間がないという場合は、POSレジを活用してみることをおすすめします。売上管理、在庫管理、棚卸機能などがついた飲食店向けのPOSレジは、初めての人にも使いやすいものとなるでしょう。また、そういったPOSレジの中にはリースかレンタルで利用できるシステムもあります。
固定費、変動費をしっかり理解し、上手にコストコントロールをすることで、利益を増やしていきましょう。
【関連記事】
カフェの経理は自分でやるべき?楽にできるクラウド会計とは
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。