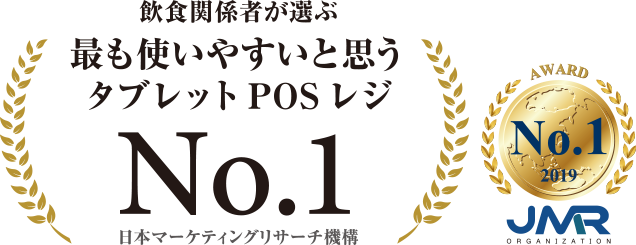今や日本の国民食ともいわれるラーメン。国内にはラーメン屋が4万店舗近くあり、そのうち個人経営が7~8割を占めています。それだけ新規参入しやすい業種といえます。とはいっても、飲食店をオープンするには食品衛生法や消防法によって定められている資格や届出が必要です。
そこで今回は、ラーメン屋である程度修業を積んだ人が独立開業する際に必要な資格と届出について説明していきます。
ラーメン屋開業に必要な資格とは?

食品を取り扱い、火を使う飲食店は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が最低限必要です。
食品衛生責任者の資格
飲食店を開業する際は、保健所に「食品営業許可申請」を提出して許可を得る必要があります。その申請書には店舗の平面図などのほか、「食品衛生責任者」の有資格者を配置することを証明する書類も添付しなければなりません。
食品衛生責任者の任務は、食品衛生法を順守して食中毒を防止することです。そのために日ごろは以下のような作業を担当します。
- 従業員への衛生指導
- 食材の保管場所や冷蔵庫の温度チェック
- トイレ掃除のチェック、掃除当番表の作成など
- 従業員の体調や身だしなみのチェック(下痢症状の有無、爪の長さや髪型など)
「食品営業許可申請」の提出時期は店舗完成の7~10日前までとされていますから、早めに資格を取るようにしましょう(資格取得法については後述します)。
食品衛生責任者になるための条件はとくになく、パート従業員でもなることができますし、店主が1人で切り盛りしているような小さなラーメン店の場合は店主が責任者を兼ねることになります。
なお、ラーメン店を開業するために調理師免許は必要ありませんが、すでに免許をもっている場合は、食品衛生責任者の資格を自動的に取得できます。
防火管理者の資格
不特定多数の人が利用する複合型商業ビルや病院などの施設では、消防法によって「防火管理者」を配置することが義務づけられています。飲食店は、収容人数が30人(席)を超える場合は防火管理者を1人選任しなければなりません。
- 収容人数が30人以上で床面積が300平方メートル以上の場合……甲種防火管理者
- 収容人数が30人以上で床面積が300平方メートル以下の場合……甲種または乙種防火管理者
甲種とは、すべての防火対象物(建物)の防火管理者となることができます。乙種は、比較的小規模な防火対象物に限られるものです。
収容人数30人以下、床面積300平方メートル以下の小さな店舗の場合は「防火管理者」を選任する必要はありません。もし、微妙な広さで収容人数のカウントのしかたがよくわからないという場合は、消防署に相談しましょう。本来は防火管理者が必要な店舗なのに「狭いから必要ないだろう」と選任しないまま開店し、火災など大事故を起こしてしまうと厳しく責任を追及されることになるからです。
資格の取得方法について

次に、食品衛生責任者と防火管理者それぞれの資格取得方法について見ていきましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者の設置義務については都道府県の管轄です。資格を取得するためには自治体や保健所が主催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することになります。講習内容は以下の3科目、計6時間で、受講料は1万円程度です。
- 公衆衛生学(1時間)……伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生など
- 衛生法規(2時間)……食品衛生法、施設基準、管理運営基準、規格基準、公衆衛生法規など
- 食品衛生額(3時間)……食品の取り扱い、食品事故、自主管理、施設の衛生管理など
講習が終わると修了証書を渡されます。
講習会はほぼ毎月開催されています。受講者が多く、定員になりしだい締め切られますから、開業に間に合わせるためには1か月前には申し込む必要があります。
申し込み方法や費用については都道府県の「食品衛生責任者養成講習会」のホームページで確認してください。なお、修了証書は全国共通なので、どこで受講しても有効です。
防火管理者
防火管理者の講習会は、市町村の消防長が主催し、消防署で実施されます。受講料はテキスト代込で甲種が7,500円、乙種が6,500円。講習内容は次の通りです。
- 甲種防火管理者(2日間)……防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管理、防火管理にかかわる訓練及び教育、防火管理にかかわる消防計画など
- 乙種防火管理者(1日間)……上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能
自分が甲乙どちらの講習を受ければいいのか判断に迷う場合は、消防署に相談しましょう。
申込み方法など詳細については一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」のホームページで確認してください。
税務署への届出

個人で事業を始める際は税務署に開業届を提出します。事業によって得た利益には所得税が課せられ、また、消費税の課税事業主に該当する場合は消費税を納めなければなりません。この所得税と消費税を納めることを税務署に届け出る必要があります。それが開業届で、正式には「個人事業の開廃業届書」といいます。
これは提出しなくてもとくに罰則はありませんが、提出することによって
- 節税効果の高い青色申告を選ぶことができる
- 店名(屋号)で銀行口座を開設できる
- 社会的信用度が高まる
など、経営上のメリットが少なくありません。
開業届は、原則として開業から1か月以内に行います。届出に必要な書類はダウンロードできるので、税務署に出向かなくても提出することができます。
労働基準局・ハローワークへの届出

従業員を一人でも雇う場合は、労災保険と雇用保険への加入手続きが必要です。労災保険とは、仕事中や通勤途中に病気・ケガを負ったときに治療費や生活費の一部を補償してもらえる制度です。これはパート・アルバイトでも加入が義務づけられています。労働時間が週に1日1時間といったわずかな時間でも加入しなければなりません。雇用した日の翌日から10日以内に労働基準局で手続きを行います。
雇用保険とは、失業した人に対して生活の安定を図るとともに、再就職の援助をするために支給されるもので、いわゆる失業保険です。労働時間が1週間に合計20時間以上あり、雇用期間が1年以上と長期就労が見込まれる従業員に加入義務が発生します。それ以下の短時間従業員は対象外となります。こちらは雇用した日の翌日から10日以内にハローワークで手続きを行います。
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)への加入については、法人は強制加入ですが、個人経営の飲食店の場合は従業員が何人いても加入は任意となります。
飲食店のパート・アルバイトの社会保険の規定・ルールを理解しておこう!
まとめ

いかがでしょうか?
事業を始めるときはさまざまな届出・手続きが必要です。「知らなかった」「うっかり見逃してしまった」では、経営者としての姿勢が問われ、社会的信用を落としかねません。成功へのチャンスを逃してしまうことのないよう、必要な資格や届出の期限・機関を書き出して、1つずつ的確にクリアしていきましょう。
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。