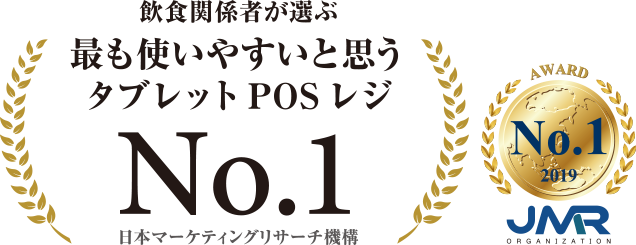飲食店の関係者が知識として備えていなければいけないことはたくさんありますが、その中でも特に重要なのが「発酵と腐敗」の違いです。この2つを分かっていないと、最悪、腐ったメニューをお客様に提供してしまう危険性もあります。
この記事では、発酵と腐敗はどう違うのか。
そして、発酵食品などを取り扱う際の注意点について紹介していきます。
発酵とは何?腐敗との違いについて

発酵食品と聞くと、納豆やみそ汁ヨーグルトを思い浮かべる人も多いと思います。しかし、そもそも発酵食品って何?と思っている人も多いでしょう。そこで、発酵とは何なのかというと、人間にとって有効な微生物が働き、物質を分解させることを指しています。
見た目や味が変わってしまうので腐敗と煮ているように感じますが、肉や魚が腐るとアンモニア臭がしますよね。しかし、発酵する場合はヨーグルトなどのように形状が変化しても食べられるものへと変わります。これが発酵食品です。ただし、線引きはとってもあいまいです。
そんな発酵食品に必要な菌として有名なのが、例えば乳酸菌です。乳酸菌には他の細菌を殺菌する力があるので、チーズやヨーグルトを作る時にも必ず使われます。他にも一昔前に流行った塩こうじの麴菌なんかも発酵食品です。
麴菌はコメや大豆を加熱すると繁殖し、アミノ酸を作り出します。また、酵母菌はパンを作る時に必ず使われますよね。その他にも納豆菌や酢酸菌などたくさんの発酵菌があります。発酵が進むと、でんぷんは糖分、たんぱく質はアミノ酸に変わり、甘味や旨味が増えてより美味しいと感じるようになるのです。
そして、発酵食品は善玉菌が多く腸内環境が整うことで便秘の解消にもつながります。また、ポリフェノールなどの抗酸化物質が含まれているのでアンチエイジング効果もあると言われています。
発酵の方法

発酵の仕組みは上記でもお話したように麴菌や乳酸菌などの微生物がたんぱく質や糖分を分解し、新しい栄養素を作り出すことです。仕組みはとっても簡単なので必要な材料を用意して酵素を活性化させれば勝手に発酵していきます。
ただし、発酵食品を作る時は以下の点に注意しなければなりません。
清潔にしよう!
発酵は腐敗と同じメカニズムでできていきます。ということは、発酵中に雑菌などが紛れ込んでしまうと、そのまま雑菌が繁殖し、発酵ではなく腐敗してしまう可能性がありますので、発酵食品を作る時に衛生面は大事です。容器は必ず消毒してしっかり乾燥させてから作りましょう。
温度管理に気を付けよう
発酵していく時の微生物はそれぞれ活動しやすい温度というものがあります。例えば、イースト菌を入れてパンを発酵させたい時だいたい30度前後で作ることが多いです。そのため、冬場はなかなか発酵しづらく、夏場は温度が高くて発酵しすぎる状況になってしまいます。発酵が進むスピードを遅くしたい時は冷蔵庫を利用すると良いです。
例えば、一昔前にカスピ海ヨーグルトが流行りましたよね。牛乳の中に種菌と呼ばれる乳酸菌を入れ、適温で1日~数日置けば勝手にヨーグルトが完成します。牛乳パックを開封して種菌を入れるだけで作ることができるのでとっても簡単でおすすめです。
その他、漬物も簡単につくることができるのでやってみてはいかがでしょうか。
飲食店で発酵食品を扱うには

飲食店で発酵食品を取り扱う際に必要な資格はありませんが、発酵に関する資格はあります。よって、資格を取っておけば発酵の知識を高めてお店作りに活かすことが可能です。例えば、発酵食健康アドバイザーは発酵食品の知識はもちろん、発酵と微生物の関係、健康と美容への効果などを幅広く学ぶことができます。
また、有機美容発酵食品マイスターは発酵と腐敗の違いや麹菌がどんな働きをしてくれるのか、などなど美容においての発酵の知識について学ぶことができます。その他にも発酵マイスターや発酵食スペシャリストなどの資格があり、発酵の知識を高め専門家として活動することもできます。
そして、発酵食品は自分で作ることもできます。中でも簡単なのはヨーグルトです。まずは、ヨーグルト作りから始めてみて慣れてきたら納豆を作ってみるのも良いでしょう。ただし、発酵食品を自分で作る時は必ず衛生面に気を付けて下さい。間違った方法で発酵食品を作ってしまうと雑菌が繁殖し、腐敗するので要注意です。
また、発酵食品は美容や健康に良いので発酵食品を取り扱えば、女子力の高い健康志向の人には目を引くポイントになります。さらに、色々な資格をとって発酵食品の知識を身に着けることで他の店舗との差別化を図ることもできます。
【関連記事】
薬味の役割知っていますか?実はすごい薬味の効果を知っておこう!
代表的な発酵食品

それでは、どんな発酵食品があるか一緒に見ていきましょう。
納豆
朝ごはんのおともに欠かせない一品ですよね。大豆に納豆菌を入れて発酵させています。
ぬか漬け
昔から台所の暗所で作られているぬか漬け。乳酸菌を発酵して作られています。
ピクルス
西洋のお漬物になります。乳酸菌で野菜類を発酵させています。
キムチ
韓国と言えばキムチですよね。日本人でも好きな人が多いですが、こちらも乳酸菌を発酵させて作られています。
いかの塩辛
酵素の力で発酵されているいかの塩辛。おつまみにも最適ですね。
鰹節
和食を作る際に出汁をとりますよね。その時に使われるのが鰹節です。実は、この鰹節はコウジカビによって発酵されて作られています。
ヨーグルト
何度も出てきていますが、ヨーグルトは自作でも簡単に作ることができます。体に良いので毎日食べている人も多いですよね。
チーズ
発酵食品の代表的な位置ではないでしょうか。乳酸菌によって発酵されています。
甘酒
一時期、甘酒が流行った時期がありましたよね。甘酒は麴菌と乳酸菌を発酵して作られています。
ワイン
1日1杯のワインで病気知らずという言葉がるように健康にも良いと言われているワイン。ブドウをワイン酵母で発酵させて作られています。
その他にも日本酒、焼酎、ビール、サラミ、アンチョビなどなどたくさんの発酵食品があります。和食には欠かせないお味噌なんかもそうですよね。
地域特産の発酵食品

では、次に地域特産の発酵食品を見ていきましょう。
すぐき漬け
すぐき漬けと聞いてもピンとこない人もいるかもしれませんが、京都の三大漬物の1つで千枚漬けやしば漬けとともにとっても有名な発酵食品なんですよ。このすぐき漬けですが、京野菜のスグキナと塩のみが使われており、乳酸発酵によって作られています。
スグキナは上賀茂を中心に生産されている大根のような形のお野菜です。昔からある伝統的な野菜で独特の酸味があるお野菜です。
へしこ
へしこは、サバなどの魚をぬか漬けにしたものです。日本海沿岸あたりでは冬の保存食として重宝されています。酒の肴としてはもちろん、ご飯のおかずやお茶漬けにも合います。
かんずり
かんずりは、唐辛子を発酵させた調味料でできあがるまでに4年はかかると言われています。塩漬けされた唐辛子を米麹で発酵させたかんずりは甘辛いのが特徴で薬味や調味料として活躍しています。
また、新潟県上越市では年間を通して多湿のエリアのためたくさんの発酵食品が作られています。有名な発酵食品としては
・浮き糀味噌
・なますかぼちゃの味噌漬け
・たらこの糀漬け
・清酒
・どぶろく
などなどです。とくに上越市は全国で最も早くどぶろく地区に認定され、国の構造改革特区制度を受けて、飲食店や民宿を経営する兼業農家が自家栽培米でどぶろくを製造することが可能となりました。
また、味噌文化が発達してきた上越にはたくさんの種類の味噌があります。中でも浮き糀味噌は、上越の黄金味噌とも呼ばれており、戦国時代から作られている味噌になります。味噌汁にした時に白い花糀の粒が浮かび上がってきますよ。米麹の甘味と大豆の旨味がとっても上品でおすすめです。
まとめ
以上が、発酵食品の種類や発酵と腐敗の違いとなります。
正しい知識を身に付けておけば、お客様に安全なメニューを提供することもできますし、発酵の特徴を押さえておくことで、新しいメニューを生み出すこともそう難しくないでしょう。
【関連記事】
代替肉の代表選手、大豆ミートはこれからの食トレンド!大豆ミートを使ったメニューもご紹介!
▼飲食店経営に関するおすすめ記事
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。