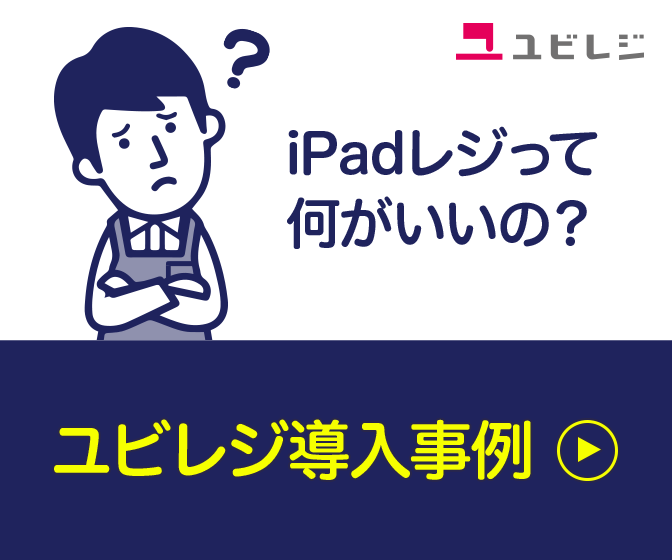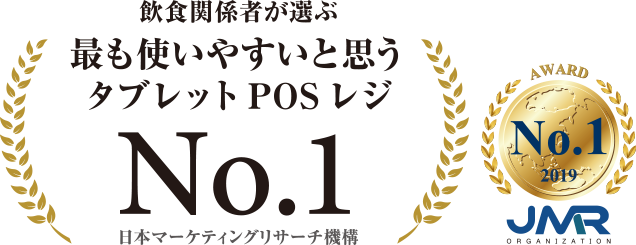季節問わず人気のアルコールメニューのひとつに、日本酒があります。全国の酒蔵こだわりのおいしい日本酒がたくさん市場に出回っているため、いろいろな料理に合わせることが可能です。今回はその中でも、東京で作られた日本酒にスポットを当ててみます。
東京の日本酒の特徴、東京のおすすめ日本酒や仕入れ方法についてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
東京の日本酒の特徴

上質な日本酒と言えば、自然豊かな地に居を構える酒蔵でつくられたものというイメージはありませんか?実は、高層ビルが立ち並ぶ大都会の東京でも、日本酒はつくられています。
東京都は、土地柄として良質な地下水や伏流水に恵まれていて、実は江戸時代から酒づくりが盛んな地なのです。江戸時代当時、酒づくりの中心は関西だったため、江戸で飲まれるお酒はおもに関西でつくられたものでした。つまり、江戸の民衆が支払った酒代は、ほとんどが関西に流れてしまっていたのです。そんな状況を変えるべく、松平定信という老中が、地元の酒蔵屋11軒に膨大な土地を与え、酒をつくることを命じました。以上の経緯によって生まれた酒が日本全国で販売されたことをきっかけに、徐々に江戸の酒造業が栄えていきました。
江戸時代から脈々と続く東京の日本酒には、どのような特徴があるのでしょうか。東京の日本酒は、富士山や秩父古生層、多摩川などから上質な地下水や伏流水を引いてつくられています。東京の日本酒は、銘柄によって味や風味は違うのですが、敢えて共通点を出すとすれば、良質な水でつくられているということでしょう。
東京の日本酒を紹介

それでは、東京の日本酒にはどのような種類があるのでしょうか。実際にご紹介していきます。
屋守(おくのかみ)
まずは、豊島屋酒造の屋守(おくのかみ)。こちらの日本酒は富士山からの伏流水を井戸からくみ上げ、それを仕込み水にしています。酒米は、日本酒に適した国産米を厳選しています。それにより、日本酒本来の旨みがしっかりと伝わり、爽やかな甘さも感じられますが、喉越しはしっかりとしたキレがあります。
多摩自慢(たまじまん)
続いて、石川酒造の多摩自慢(たまじまん)。こちらの日本酒は、色も味も濃い目となっています。ただし、濃いだけではなく、シンプルでさっぱりとした味わいでもあります。酸味や辛みは少なく、甘みを多く感じます。癖が少ないので、飲みやすい日本酒といえるでしょう。
澤乃井(さわのい)
最後は、小澤酒造の澤乃井(さわのい)。こちらの日本酒は、秩父古生層から汲まれた豊かな仕込み水でつくられています。酒蔵の敷地内には年代別に3種類の酒蔵があり、歴史的にも価値のある酒造となっています。穏やかで、飽きがこないような味わいでありながら、最後に辛みを感じる後味の良さが印象的です。
今回は東京の日本酒を3つ紹介しましたが、東京の日本酒はこれだけではありません。お気に入りの日本酒を見つけられるように、いろいろと飲み比べてみるようにしましょう。
日本酒の基本の飲み方

日本酒の基本的な飲み方をご存じの方はどれだけいるでしょうか?なんとなく日本酒を提供している飲食店経営者も多いと思います。
日本酒の基本的な飲み方は温度を変えたり、ワイングラスや升に注いで飲むなどさまざまあります。
基本的な飲み方を押さえておくとお客様に日本酒をより楽しんでもらい、リピーターにつなげることができます。
冷酒
冷やした日本酒のことを冷酒と呼び、冷酒はシャープな口当たりが魅力です。
また、冷酒は冷やす温度によって呼び方が異なります。
- 雪冷え(5℃)
- 花冷え(10℃)
- 涼冷え(15℃)
常温
日本酒における常温は20℃〜25℃くらいです。
長期間熟成した日本酒は常温でいただくと甘みが増して美味しいです。特に純米酒は米の風味が口いっぱいに広がります。
ぬる燗
日本酒を温めて飲む方法です。温めた日本酒は良い香りが立ちます。純米酒や吟醸酒に向いており、まろやかな甘みと香りが特徴です。
温度は後述する熱燗ほど熱くありません。ぬる燗の温度別の呼び方は以下の通りです。
- ぬる燗(40℃)
- 人肌燗(35℃)
- 日向燗(30℃)
熱燗
熱燗は日本酒の旨味と甘さがより強くなり、冬に提供すると喜ばれます。その一方、風味や酸味が重いと感じるお客様も多いです。
熱燗の温度別の呼び方は以下の通りです。
- 飛びきり燗(55~60℃)
- 熱燗(50℃)
- 上燗(45℃)
ワイングラス
ワイングラスの「あの形状」はワインの香りを楽しむために作られました。
ワイングラスで日本酒を飲むと、おちょこやグラスとは違った香りを楽しむことができます。
日本酒に飽きてきたお客様に新しい楽しみ方を勧めてみると良いでしょう。
升&グラス
升の中にグラスを置いてそこに溢れるくらい日本酒を注ぐ飲み方は、江戸時代から引き継がれています。
グラスで飲みつつ升の中に溢れた日本酒も飲む豪快さは、おめでたい席にぴったりです。お祝い事のあるお客様が来店した時は勧めてみましょう。
初心者が飲みやすい日本酒の飲み方

日本酒を飲み慣れていないと、「味が苦手で…」という人もいます。そういう場合は前述した飲み方をしても楽しめません。
日本酒初心者のお客様には以下の方法を勧めてあげると良いでしょう。カクテルのように気軽に日本酒を楽しむことができます。
吟醸酒でフルーティーに
低温でじっくり発酵させて香りを閉じ込めた吟醸酒というお酒があります。
フルーティーな味わいなので、日本酒を苦手にしている人でも飲みやすく、女性人気が高いです。
バニラアイスと
バニラアイスに日本酒をかけて飲むと和風アフォガートのような味に変化します。
アイスにかける日本酒は、吟醸酒や純米酒を選ぶのが定番です。スイーツや甘いお酒が好きなお客様に勧めてみてはいかがでしょうか。
東京の日本酒を仕入れるには?

実際に東京の日本酒を店舗で提供するとなった場合、どうやって仕入れたらよいのでしょうか。
たとえば、東京の日本酒をネットショップで仕入れるという選択肢もあります。ネットショップだと実際にお店へ出向く手間が省けますし、扱っている日本酒をリストで見ることもできます。簡単で分かりやすいというのは、大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、仕入れてみるまでどんなお酒かわからないというデメリットもあります。いくら商品説明やレビューがあるからと言って、それだけではお酒の味や特徴は伝わり切れません。ネットショップで仕入れる際には、実際に自分の口で試飲したことのある東京の日本酒を仕入れるといいでしょう。
おすすめは、酒造に実際に出向いて、仕入れの交渉を行うことです。多くの酒蔵では酒蔵見学を行っており、そのお酒がどのように出来上がるのかを見学することができます。お酒の製造工程をみることで、味に対してのイメージも広がってくるでしょう。
酒造で直接交渉をすることで、値引の交渉もできるかもしれません。もちろん、値引き交渉に応じてくれるかは酒造ごとで異なりますから、値引き交渉はできないと思って、ダメ元で確認をしましょう。
東京の日本酒を仕入れる方法はいくつかありますが、一番おすすめな方法は、酒造に実際に出向いて自分で交渉する方法でしょう。
東京の酒蔵を訪ねてみよう

実際に東京の酒蔵を訪れるとしたら、どのような準備が必要でしょうか。
まずは、酒蔵見学が可能な酒蔵かどうかを確認しなければなりません。一番手っ取り早い確認方法は、酒造に電話をして確認することです。電話をする時間がなければ、インターネットで調べてみるというのも良いでしょう。最近では、SNSで酒蔵見学のイベントを告知しているところもあったりと、インターネット上に情報が載っている場合がほとんどです。
酒蔵見学をできることがわかったら、確認しておきたい項目がいくつかあります。
まずは、参加人数の下限上限です。酒蔵によっては、酒蔵見学の参加人数を制限している場合もあるので、前もって確認しておくようにしましょう。
次に予約方法です。酒造によって予約方法は異なります。電話のみの受付だったり、メール、ホームページなど、いろいろな予約方法があるので、それも確認しておきましょう。
最後に、酒蔵見学の予定時間です。酒蔵見学はイベントとして行われていることも多いので、時間が指定されていることも多々あります。スケジュールを確認して、時間に余裕がある日に予約をとるようにしましょう。
予約も取れ、酒蔵見学の日にちが決まったのなら、その酒造でつくられるお酒に関する情報を事前に予習しておくことも大切です。頭に情報をいれてから酒蔵を見学した方が、東京の日本酒に対する理解度を深めることができるでしょう。準備をしっかりとおこない、有意義な酒蔵見学となるようにしてください。
まとめ

いかがでしょうか?
東京と言えば「人の多い都会」で、日本酒のイメージを持たれる方は少ないかと思います。しかし、東京は江戸時代から続く酒造りの盛んな地のため、思いの外日本酒の種類がたくさんあるのです。それぞれの酒蔵によって製造方法に違いがあるので、いくつか酒蔵見学に行って吟味することをおすすめします。お客様に最高の時間を味わっていただけるよう、どの東京の日本酒を取り入れるか、リサーチをしっかりおこなってくださいね。
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。