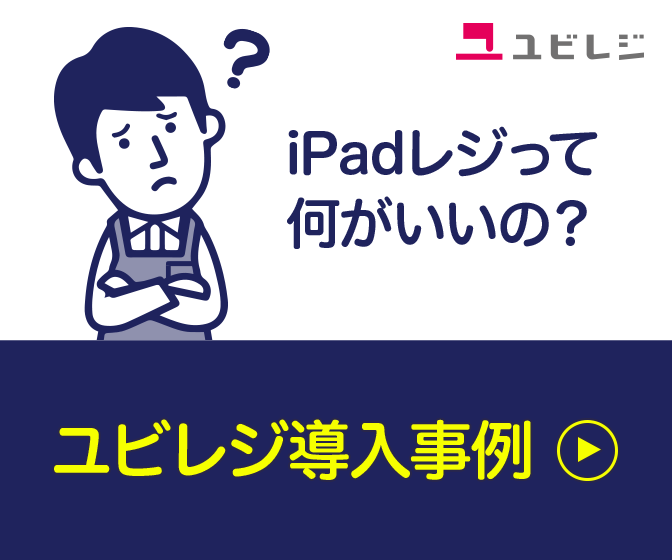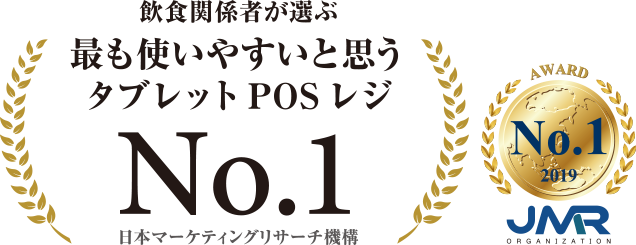昨今では、日本酒より洋酒か焼酎を飲まれる機会が多いという方も多いのではないでしょうか?
しかく、多くのお酒の台頭で飲む機会が減ったとはいえ、日本酒を好んで飲まれる方も多くいらっしゃいます。では、日本酒と一口にいっても、実は様々な種類があることをご存知ですか?
日本酒には様々な種類がありますが、かといって決して難しい事はなく、 ワインのように専門的な知識も必要ありません。
日本酒に関する簡単な知識をつければ、お客様の好みやお店で提供する料理に合った日本酒を提供できるようになります。 そこで今回は、日本酒をもっと身近に感じていただけるよう、日本酒の種類を紹介しながら、お店に合った日本酒が選べるよう、日本酒の魅力を伝えたいと思います。
2つの分け方で簡単に覚えよう

まずは基本をみていきましょう。日本酒は原料と精米歩合で、以下の8種類に区別されます。
- 本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ)
- 吟醸酒(ぎんじょうしゅ)
- 大吟醸酒(だいぎんじょうしゅ)
- 純米酒(じゅんまいしゅ)
- 純米吟醸酒(じゅんまいだいぎんじょうしゅ)
- 純米大吟醸酒(じゅんまいだいぎんじょうしゅ)
- 特別純米酒(とくべつじゅんまいしゅ)
- 特別本醸造酒(とくべつほんじょうぞうしゅ)
| 特定名称 | 使用原料 | 精米歩合 | こうじ米使用割合(新設) | 香味等の要件 |
|---|---|---|---|---|
| 吟醸酒(ぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が良好 |
| 大吟醸酒(だいぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好 |
| 純米酒(じゅんまいしゅ) | 米、米こうじ | - | 15%以上 | 香味、色沢が良好 |
| 純米吟醸酒(じゅんまいぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が良好 |
| 純米大吟醸酒(じゅんまいだいぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好 |
| 特別純米酒(とくべつじゅんまいしゅ) | 米、米こうじ | 60%以下又は特別な製造方法(要説明表示) | 15%以上 | 香味、色沢が特に良好 |
| 本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 70%以下 | 15%以上 | 香味、色沢が良好 |
| 特別本醸造酒(とくべつほんじょうぞうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 60%以下又は特別な製造方法(要説明表示) | 15%以上 | 香味、色沢が特に良好 |
日本酒の種類を理解するには、いくつかのポイントがあります。 まず、第一のポイントは、「純米」という言葉が入っているものは「醸造アルコール」が入っていないお酒を指します。醸造アルコールは、日本酒にキレ味と辛口な風味を出すアルコールの材料のことで、「純米酒」はこれが配合されていません。
「醸造アルコール」とは甲類焼酎のようなもので、日本酒に入れることで香りが良くなります。また味わいもスッキリとしたお酒(辛口)になりやすく、品質も安定します。
つまり、本醸酒、吟醸酒、大吟醸がこの部類に入るわけです。
同じお米と米麴で作られるのに、製造工程で醸造アルコールが入るかどうかで種類が分かれます。「本醸造」よりもお米を磨いて仕込んだものが「吟醸」、その上が「大吟醸」となります。逆に醸造アルコールを入れてない日本酒は「純米酒」と区別されます。
「純米酒」よりもお米を磨き、仕込んだものが「純米吟醸」になり、その上が「純米大吟醸」となります。 日本酒は製造過程で「磨いたお米」を使用しますので、そのお米を磨けば磨くほど、高級になっていき、味わいも繊細になっていくのです。
さらに、同じお米でも産地によって風味が変わってくるところも、日本酒の面白いところです。次項よりさらに詳しくみていきましょう。
原料の違いで種類がわかれる

ご存知のように、日本酒の主な原料はお米で、お酒造りに使用するお米を一般的に酒米と言います。日本酒を醸造する際、主に麹米として使うのが酒米であり、それに適するお米を「酒造好適米」と言います。ワインが食用の葡萄ではなく、ワイン用の葡萄と分けて生産されるのとよく似ています。
日本酒は特に、お酒造りに使うお米に特有の品質が求められます。通常の食用米と比べて、一般的に粒が大きいのが特徴です。大粒で、中心部の「心白」という白い部分が大きく、たんぱく質含有量が低く、粘りよい品種になります。これが日本酒の特徴を生み出します。
日本酒造りで、大粒が好まれる理由としては、精米の時に表面を大きく削る必要がある為、粒の小さな米だとすぐに砕けてしまうからです。
大吟醸などの香り高い日本酒を造るためにはさらに精米の表面を削るので、それに耐えうるお米が必要になってきます。
純米酒と本醸酒の原料の違いを見てみましょう。
・純米酒
純米酒は米、米こうじ、及び水を原料としたお酒で、吟醸酒とは違い、精米歩合に関する決まりがありません。前述したように、醸造アルコールも入れません。
米こうじは使用する白米全体の15%以上であること、そして3等以上に格付けされた玄米、もしくはこれに相当する玄米が使用されていることが条件となっています。
・本醸酒造
これに対して本醸造酒は、精米歩合70%以下の白米、米こうじ、水、さらに醸造アルコールを使用した日本酒をさします。その中でも香味や色沢が良好なものにもちいられる特定名称酒となっています。加える醸造アルコールに関しては、白米1トンに対して120リットルまで添加してもよいこととなっています。
精米歩合で種類がわかれる

日本酒は精米歩合によっても種類が分かれます。精米歩合とは、そのお米がどれだけ削られているか?を表す数値になります。例えば精米歩合40%とは、なんとお米の周りを60%も削っているということになります。 なぜ、そんなことをするかというと、お米を削って心白と呼ばれる米の中心部を使うことで、雑味のないお酒を作り出す事ができるからです。よってこの精米歩合の%が高いほど、雑味がなく、まろやかでランクも上級の日本酒になっていくわけです。同時に前述したように、精米歩合が何%かで、日本酒の種類も分けられてくるわけです。
具体的にお酒別で見てみましょう。
吟醸酒
吟醸酒とは、精米歩合が60%以下の白米、米こうじ及び水、またはこれらと醸造アルコールを原料としたものを吟醸造りによって製造した清酒の事です。固有の香味、色沢が良好なものに用いることができる特定名称酒となっています。
大吟醸
吟醸酒の中でも、精米歩合が50%以下の原料を使用しているものが大吟醸と呼ばれる日本酒です。
本醸造酒、特別本醸造酒
本醸造酒の中でも特に香味や色沢が良好なものであり、なおかつ、使用される原材料や製造方法についてはっきりと説明明記されているものに対して用いることができる特定名称酒です。精米歩合60%以下となる場合となっています。
特別純米酒
純米酒の中でも、香味、色沢が特に良好であるものをいいます。また精米歩合は60%以下、もしくは使用原材料や特別な製造方法に関する説明、表記が必要となっています。
日本酒の種類別特徴

色々な定義で種類分けされている日本酒ですが、実際の風味や特徴は種類によってどうちがうのでしょう?以下、各特徴をまとめてみました。
吟醸酒
リンゴやバナナといったフルーティーで華やかな香り成分は吟醸香が特徴です。
これは低温で長時間発酵することによって生み出すことが可能となっています。また、この吟醸香を引き出すために醸造アルコールを加えます。
大吟醸
吟醸酒にくらべてさらに低温長時間での発酵を行い、より素晴らしい吟醸香を出させます。固有の香味、色沢が特に良好とされるものに用いることができるのが大吟醸になります。
純米酒
濃厚な味とコクで、米本来の旨味が特徴です。特別純米酒はこれに精米歩合が60%以下とう条件がつき、より深みのあるお米の風味が特徴です。」
また、純米酒や吟醸酒以外にも以下のような日本酒があります。
スパークリング日本酒
その名の通り、日本酒の発泡酒です。
食前酒としてだけでなく様々な食事にも相性が良いお酒で、近年、若い女性を中心に人気が広まっています。
炭酸ガスを注入する方法と、瓶内で二次発酵させる方法があります。
にごり酒
にごり酒とは、発酵をおえる前のもろみを濾さない、もしくは軽く濾すだけで造られたお酒です。
そのため透明にはならず、にごったお酒となるので、にごり酒と呼ばれるようになりました。
味は濃厚で甘口というものが多くなっています。ほとんどが火入れを行わないため瓶内で二次発酵がおこり発泡性のあるものが多くなります。
【関連記事】
にごり酒は冬の一押し!特徴、飲み方、おすすめにごり酒10選!
味や香りの違いでの4分類

日本酒は大吟醸や純米酒などに分かれているのですが、実は、味や香りで4つに分けられています。それぞれをみていきましょう。
薫酒(くんしゅ)
大吟醸が多く該当するのですが、このタイプやフルーティーな香りが特徴となっています。最近は、流行の傾向にあり、多くの方から人気を集めています。
香りが高く、味が淡いのが特徴の日本酒となっています。
爽酒(そうしゅ)
文字からも分かる通り、すっきりとした爽やかな味わい。飲みやすさが特徴のお酒となっています。本醸造や普通酒が該当することが多く、淡麗で辛口なタイプとなっています。辛口なので飲みにくいのではと思う方もいるでしょうが、その真逆で香りこそは低いものも、味が淡く飲みやすいお酒となっています。
醇酒(じゅんしゅ)
純米系の日本酒が該当します。お米の旨みやコクがハッキリと分かるタイプのお酒となっています。非常に味が濃いので、味付けの濃い料理と一緒に飲んでも、料理の味に負けることなく、お酒を楽しむことができます。
それでいて、香りが低く、味が濃い為に、お酒好きにはたまらない種類と言えるでしょう。その逆で日本酒に飲み慣れていない方は、少ししんどいかもしれません。
熟酒(じゅくしゅ)
古酒や熟成酒のことを言います。とろりとした飲み口となっているので、好き嫌いは分かれるかもしれません。香りが強く味も濃いのが特徴となっています。
覚えてもらいたい日本酒の種類

前項で日本酒の4つの分類について紹介しましたが、お酒の種類や名称はまだまだたくさんあります。いくつか、下記に紹介していくので、気になるお酒があれば、ぜひ一度飲んでみて下さい。
・原酒
絞ったお酒に水を加えることなく、瓶に詰めたタイプ。度数は20度前後が多く、冷やして飲むことで味が引き立つお酒。ロックで飲むのがお勧めです。
・中取り
日本酒を絞る時、「あらばしり」の次に出てくる部分を瓶に詰めたタイプとなっています。新酒の時に市場に出回ることが多いです。
・あらばしり
日本酒を絞る際、一番最初にでてくる部分を積めたものとなります。香りが良く新種の時に出回ります。
・おりがらみ
絞ったばかりの日本酒の濁りを「オリ」というのですが、普通は、オリが沈殿してからろ過していくのが一般的。しかし、おりがらみでは、オリが沈殿する前に瓶に詰めたものとなります。コクのあるお酒が多いです。
・新酒
文字通り、完成したばかりの日本酒。フレッシュな味わいが特徴的となっており、多くの方から愛されています。
・生酒
加熱処理を行わない日本酒となっています。酒好きにはたまらない程の美味ではありますが、味が変わりやすく常温保存ができません。
・ひやおろし
春から夏に熟成させて、秋に出荷されるお酒のことを言います。1年を通して、もっとも美味しいと言われるお酒となっています。
・にごり酒
目の粗い布で絞ったものが一般的にはにごり酒と言われています。日本酒は透明なイメージがありますが、にごり酒に関しては白くにごっています。
・生貯蔵酒
生酒のままタンクにいれておき、出荷する前に一度だけ日を入れるお酒のことです。市場には春から夏に出回っています。
以上が、日本酒の種類と味の違いとなっています。
一口に日本酒といっても、その製造過程や保存方法によって香りや味が大きく違ってきます。それを楽しめるのも日本酒の魅力ですよね。
同じ大吟醸であっても、製造過程が違うと、味も驚くほど変わるので、気になった種類のお酒があれば、ぜひ一度手を伸ばしてみて下さい。
特徴によって合う料理が違う

それぞれの日本酒にコクや香りなど特徴があり、種類によって相性のよい食べ物も違ってきます。具体的に日本酒を吟醸酒系、純米酒系、本醸造酒系に分け、それぞれの種類に合った料理を見てみましょう。
吟醸系日本酒に合う料理
吟醸系日本酒の最大の特徴は、吟醸香と言われるフルーティーな香りです。
その華やかな香りは、甘口から辛口まで様々な味わいのものがあり、素材そのものを活かした料理がおすすめです。
特に海鮮、白身系、良質のかまぼこなどの料理が特によく合います。白身魚の刺身から貝の酒蒸し系は特に相性が良く、あっさりとした味付けでも素材の香りや特徴を存分に引き出してくれます。
純米系日本酒に合う料理
お米の風合いを直接、感じることが出来る純米酒系の日本酒は、使われているお米の香りや旨みを存分に感じさせてくれるのが最大の特徴です。
純米酒系のお酒にぴったりの料理は、味付けのしっかりしたものがおすすめで、洋食にも良く合います。
しっかりと味付けした煮物から、クリームシチュー、さらにはチーズなどに代表される乳製品などと幅が広く、タレ系の焼き鳥、サバの味噌煮をはじめとする魚の煮つけなども非常によく合います。
本醸造系日本酒に合う料理
辛口、淡麗の味わいを特徴とする本醸造系の日本酒は、実に様々な料理と相性が良いと言えるでしょう。
本醸造酒には、味付けのあっさりとした冷ややっこなどがおすすめですし、味付けのこってりとしたものでも、相性は決して悪くありません。
おすすめの料理としてはやはり和食でしょう。豆腐料理や焼き物煮物、蒸しものなどとは非常に相性が良いです。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
同じ日本酒でも、実に様々な違いと特徴があることが分かりました。日本酒ごとの違いや特徴を把握し、自分のお店にあった日本酒や料理を提供できるようになりましょう。
そうして、「日本酒を飲むならここ!」とお客様に選ばれるお店を目指しましょう!
【関連記事】
利酒師で日本酒の魅力もお店の魅力もアップできる!
福島の日本酒は美味くて人気ってホント!?仕入れ方法や特徴を紹介
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。