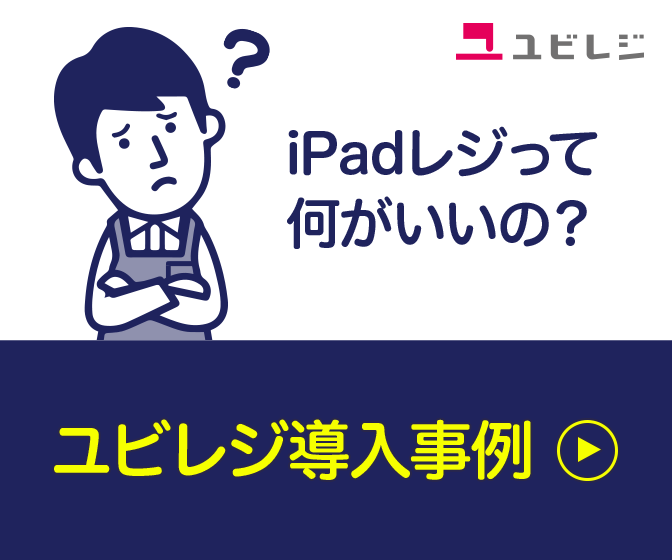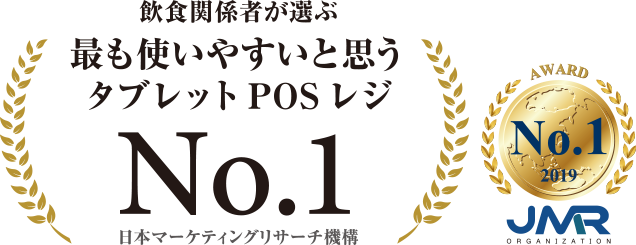自家製果実酒は、お酒を扱う飲食店で是非とも作っておきたいアイテムの一つです。自家製果実酒の良いところは、規制製品よりも安く作れるので、原価率が非常に良いという点と、お店によって個性の違う果実酒が造れるので、他店との差別化が図りやすいという点です。
では、自家製果実酒はどうやったら造れるのでしょうか?その方法をご紹介します。
果実酒とは

果実酒とは、果汁から作られた醸造酒のことで、一般に原料の果実の酸味や風味を持つのが特色のお酒です。本来の果実酒は、果汁を発酵させて作ったもののことを言いますが、果実を発酵させることなくその風味だけを抽出したもののことも、果実酒と呼ばれます。しかし、日本の酒税法では、果実を原料として発酵させたものを果実酒と規定しています。(酒税法第3条)
梅酒だけじゃない!果実酒にはなにがある?

果実酒というと一般的にすぐ「梅酒」をイメージされる人も多いでしょう。確かに、梅酒は日本人にとってお馴染みの果実酒ですが、果実酒はそれだけではありません。果実酒の定番といえば、上記の梅酒、ぶどう酒、りんご酒が挙げられますが、まだまだ他にも色々な果実酒があります。
マンゴーやゆず、桃、みかん、なし、さくらんぼ、杏、いちご、ザクロ、クロスグリ(カシス)のような比較的、果肉がやわらかいものを原料とする果実酒です。
果実酒の原価

果実酒の原価はその年の使うフルーツと提供する値段で変わります。
「果実酒のレシピ」は
果実:500g
ホワイトリカー:900g
氷砂糖など:100g
の割合で作られることが多いのでこれを基準に計算してみましょう。
例えば
果実:500g(100g 400円 × 5個) = 2,000円
ホワイトリカー:900ml = 1,000円
氷砂糖:100g = 100円
としたら
2,000円 + 1,000円 + 100円 = 3,100円
となり、原価は合計で3,100円となります。
果実酒をストレート・ロック、何かで割るにしても、1杯60mlで600円で提供するとします。
果実汁も加わるので1,000mlほどの果実酒を造ることができます。
1,000ml ÷ 60ml =16〜17杯 これだけのドリンクが造れるわけです。
これを600円で販売したら 600円 × 17杯 = 10,200円となります。
これを原価率計算すると
原価3,100円 ÷ 販売価格合計10,200円 = 0.30
つまり、原価率は30%となります。
販売価格が高ければ、さらに原価率は良くなりますので、仕入れ値と相談しながら販売価格を決めることが、果実酒の原価を抑えるポイントになります。
他店と差別化!自家製の果実酒を作る5つのポイント

果実酒造りは何だか難しそうに聞こえますが、実は簡単に造ることができます。自家製果実酒を作るポイントは5つあり、そのポイントを押さえれば、意外に簡単にできるのです。
・ポイント1:旬のものを選ぶ
果実は、その時期に旬の新鮮なもの、傷がなくきれいなものを選んでください。熟しすぎたものは濁りやすいので避けた方が良いでしょう。また、旬の食材は市場にたくさん流通していますので、安く仕入れることができ、原価を抑えることができますし、季節感たっぷりのメニューとしてアピールすることもできます。
・ポイント2:よく水気を取る
果物は洗った後、水気を十分にふき取ってから漬けましょう。
・ポイント3:容器のサイズ
果実酒の漬け込み容器の瓶は、例えば使用量1.8Lの場合、容器は約4L程の広口瓶が最適だと言われています。ガラス製を選びましょう。(漬け込みの期間でちょうどいい色合いを見ることができるため。)よく洗浄して、十分な瓶をご使用ください。
・ポイント4:アルコール度数と糖分
果実の特徴を最も活かしたお酒をつくるには、「ホワイトリカー」(アルコール35%)が適しています。また、糖分も重要となり、最も適しているのは氷砂糖です。またグラニュー糖等でも作ることができます。はちみつ等を少量加えるとう味わいが楽しめます。
・ポイント5:保存場所
果実を漬け込んだら、風とおしのよい、温度変化の少ない冷暗所で保存しましょう。漬け込んだ年月日、果実名、生薬名を書いたラベルを貼っておくと便利ですので忘れずに貼っておきましょう。
以上の5つのポイントを踏まえるだけで、美味しい自家製の果実酒を作ることができます。
定番果実酒の作り方

果実酒は実に様々な酒類がありますが、中でも定番の人気果実酒があります。具体的な例と作り方を挙げていきます。
マンゴー酒の造り方
材料
・マンゴー500g
・氷砂糖 100g
・ホワイトリカー 35度 900ml
マンゴーは大きいので2L以上の容器が必要になり、容器は必ず煮沸消毒してください。消毒の仕方は、この保存ビンがゆったり入るくらいの大きな鍋に、たっぷりの水を入れ保存ビンを沸騰させます。沸騰したお湯に入れると、割れる場合があって危険ですので、必ず水から入れてください。
マンゴーはヘタがある方を上におき、果実が薄くなっている方を立てます。中心部分に種があるので、中心に親指をおき、その横を切ります。同じように逆側も切ります。
煮沸消毒した保存ビンに、3枚に卸したマンゴーとホワイトリカーを入れます。完熟したマンゴーの場合は糖分が高いので、氷砂糖は必要ありませんが、そうでない場合は100gを目安に調節してください。漬けてから1ヶ月後くらいから飲むことができますが、熟成させるほどおいしくなるそうです。
ゆず酒の造り方
材料
・ゆず 500g
・氷砂糖 100g
・ホワイトリカー 35度 900ml
1.8L以上の容器を用意し、マンゴー酒の時と同じように容器を煮沸消毒します。
ゆずは1個だけ、ぬるま湯でキレイに洗い、薄く皮をむきます。残りの柚子は皮と中ワタを取り、2〜3分割くらいに割って入れます。煮沸消毒した保存ビンに、柚子の皮1個分と残りの果実、氷砂糖、ホワイトリカーを入れます。
飲み頃は、漬けてから1~2ヶ月後くらいですがさらに漬け込むと、3か月目には、蓋を開けて見ると、柚子の爽やかな香りが広がります。お酒の方も、柚子種に多く含まれるペクチンの効果で、トロンとしてきます。飲む際は、漬けていた柚子を引き上げ、キッチンペーパーをザルに敷いて果実酒を漉してください。柚子の風味と味がしっかり出て実に爽やかで美味しくなります。また、引き上げた柚子は、ジャムにしてデザートなどに活用するのも良いでしょう。
梅酒は果実酒の中でも一番人気のある果実酒です。漬け方も日本酒、ブランデー、麦焼酎などたくさんの種類があるようですが、まずは定番な焼酎でつくる梅酒の作り方です。
焼酎でつくる梅酒
材料
・青梅 500g
・氷砂糖 100g
・ホワイトリカー 35度 900ml
梅酒はたくさん漬け込んだほうがより風味を引き出せるので、2L以上の容器を用意した方が良いでしょう。容器を煮沸消毒します。
青梅は水でキレイに洗い、爪楊枝や竹串で、青梅に傷をつけないようにヘタを取ります。傷が付くと、ニゴリの原因になりますので慎重に行いましょう。ヘタを取った青梅を、キッチンペーパーや布巾で水気をキレイに拭き取り、煮沸消毒した保存ビンに、青梅、氷砂糖、ホワイトリカーを入れます。梅酒の甘さの目安として、飲料水の「午後の紅茶レモンティー」の糖度6.3度を目安にすると良いでしょう。
漬けてから3ヶ月後くらいから飲めるようになりますが、長く漬けておくほどおいしくなります。漬け込み1年目までの時は、氷砂糖を少なくしすぎたかな?と思うくらい、さっぱりした味わいを楽しめます。2年目に入ってからは、甘さも丁度良くなります。これぐらいの時期になると、甘さも飲料水の「ヤクルト」の糖度、18.1度となります。1年2ヶ月後は甘さと酸味が調和し、すっきりとした梅酒に仕上がります。飲みながらさらに熟成させていけるのが、梅酒の良いところでしょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか?思ったより難しくなかったのではないでしょうか?
是非、自身のお店にしかないオリジナルの自家製果実酒を作って、他店との差別化を図り、集客につなげてみてはいかがでしょうか。
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。