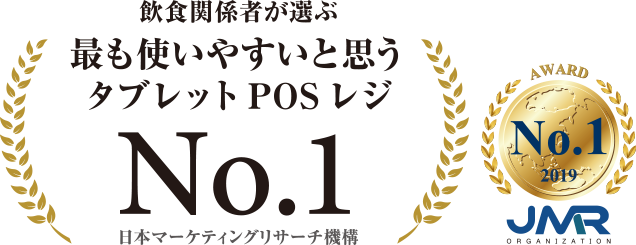売上高に対する利益を表す「利益率」は、飲食店経営を分析するうえで欠かせないデータです。また売上総利益や営業利益、原価率などをあわせて見ることで、経営上のさまざまな問題点を抽出できます。分析結果を活用し、店舗の売上アップやコストダウン、経営ノウハウの蓄積につなげましょう。
当記事では経営指標となる利益の種類やその算出方法、飲食業の利益率目安、さらに飲食店の利益率向上のための施策などを解説します。
飲食店の経営指標となる利益の種類と計算方法
飲食店の利益には「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」の5種類があります。損益計算書にも記載するこの5種類の利益について解説します。
売上総利益(粗利・粗利益)
「売上総利益」とは、売上高から「売上原価」を差し引いて残った利益です。飲食店では、提供した料理やドリンクなどで得た利益を意味します。

売上総利益は店舗のおおまかな利益を表し、商品力の大きさにも比例します。売上総利益から判断できる経営戦略は次のとおりです。
・新メニューの考案や既存メニューの改善
・原材料費の見直し
営業利益
営業利益とは、売上総利益から「販売費および一般管理費(以下、販管費)」を差し引いて残った利益です。そのため、売上総利益より経営実態に沿った利益になります。

販管費とは、「経営や管理、販売促進などの活動にかかる費用」を意味し、飲食店では以下のような費用となります。
・人件費
・賃貸料(店舗の家賃)
・水道光熱費
・広告宣伝費
・消耗品費
・リース料
・通信費
・保険料
など
もし営業利益がプラスなら本業において黒字経営、マイナスなら赤字経営になります。営業利益の増減には販管費が大きく影響するので、経営戦略としては販管費の内訳を分析することが重要です。
経常利益
経常利益とは、本業以外で発生した利益(営業外収益)・損失(営業外費用)を、営業利益に加えて算出する利益です。財務活動で発生した損益というイメージです。

税引前当期純利益
税引前当期純利益とは、税金を支払う前の利益です。事業と関係のない収益・損失である「特別利益・特別損失」を経常利益に加えて算出します。

当期純利益
当期純利益とは、税引前当期純利益から支払う税金を引いて残った利益です。最終的に店舗がどれだけの利益が出したのかを表します。

固定資産税や印紙税などは、販管費の「租税公課」として処理し、消費税は、貸借対照表の負債の部への計上となります。
当期純利益は、今後のために蓄えておく利益剰余金(内部留保)とする、新メニュー開発や従業員教育のために投資するなど、さまざまな使い道があります。
飲食業界の利益率の計算方法と目安
飲食業界の利益率計算方法と利益率の目安を説明するとともに、業界別の平均利益率からみた飲食業界の利益率についても解説します。
利益率の計算方法
飲食店における利益率は、売上高営業利益率(売上に対してどれくらいの営業利益だったのか表す比率)で表すことが一般的で、算出式は次のとおりです。

またもう1つの指標として使えるのが、売上高÷売上総利益で算出する「売上高総利益率(粗利率)」です。ハンバーグ1個900円・売上総利益が600円であれば、600÷900で売上高総利益率約66.6%。つまり7割弱の粗利だとわかります。
【業界別】利益率の目安
総務省が2020年に実施した「2020年(令和2年)個人企業経済調査 結果の概要」によると、卸売業の年間営業利益率は7.4%、衣料品・その他の小売業は10.5%でした。高い値を示したのは、その他サービス業の不動産業・物品賃貸業34.1%、医療・福祉の33%です。
飲食サービス業の年間営業利益率は12.9%でした。業界全体の平均の16.1%より約3%低くなっています。
仮に月商1,000万円でも、売上原価・販管費を差し引くと129万円しか残らない計算です。
とはいえ飲食業界の場合、経営スタイル・方針の違いで利益率の目安は異なります。たとえば薄利多売で回転率を上げる居酒屋は、売上高を増やすことで利益を出すスタイルです。一方、高級路線の料亭は、売上高よりも1人あたりの販売単価・客単価を高めることで利益につなげます。
【参考】2020 年(令和2年)個人企業経済調査(総務省)
https://www.stat.go.jp/data/kojinke/kekka/pdf/2020gaiyou.pdf
飲食店の利益率向上のための施策
売上高は世情や顧客に依存しますが、利益率は経営者の工夫次第で向上が望める指標です。利益率向上のための3つの施策を解説します。
固定費・変動費を抑える
売上原価や販管費に当たる固定費・変動費を抑えることで、手元に残る利益を大きくできます。
固定費とは、商品や売上、季節などにほぼ影響されない費用です。家賃やリース・レンタル賃料、減価償却費などが当てはまります。金額が固定で、削減が難しい支出です。
変動費は、商品や売上、季節などで金額が変わる費用です。原材料費や人件費、水道光熱費の一部などが当てはまります。削減しやすいのは変動費のほうです。
たとえば原材料費削減のためには以下の施策が考えられます。
・一括仕入による割引の利用
・原材料のランクを下げる
・仕入れ量の見直し
・仕入れルートの見直し
・メニューやレシピの見直し
など
売上高÷売上原価で「原価率」を算出すれば、売上に対する原材料費の割合がわかります。飲食店の適切な原価率は25~30%と言われますが、実際は経営スタイルによって異なるので注意が必要です。
なお飲食店経営では、最も大きなコストである原材料費(Food)と人件費(Labor)の合計を表す「FLコスト」が重要です。売上高に対するFLコストの割合が「FL比率」で、理想的なFL比率は60%±5%になります。食材の選定やスタッフ・アルバイトの給料などを見直し、自店舗にとって適切な比率となるようコントロールしましょう。
固定費や変動費をどこまで削減すべきかの指標となるのが、「損益分岐点」です。損益分岐点とは、収益と費用のそれぞれ±0の地点のことで、次の式で計算します。

利益率の高いメニューを多く提供する
提供するメニューを高利益率のものに変更することでも利益率アップは可能です。以下は高利益率のメニュー、いわゆる原価が安い料理の例です。
・たこ焼き・お好み焼き・パン・パスタなどの小麦粉関連の料理
・フライドポテトやポテトサラダなどのじゃがいも料理
・アイスクリーム
・お酒・ソフトドリンク・コーヒーなどの飲料全般
・枝豆 など
加えて、セットメニュー販売やセットで頼みたくなるメニュー展開などの工夫も取り入れましょう。
在庫管理を徹底して食材のロスを減らす
食材ロスを減らすことは、利益率の高い経営のために必須といえます。
とくに生鮮食品や賞味期限のある原材料を取り扱う飲食業にとって、在庫管理は非常に重要なポイントです。もし廃棄すべき食材を提供して衛生事故が発生しようものなら、食材ロスどころか営業停止や損害賠償請求につながります。
飲食店の在庫管理の基本は次のとおりです。
・古い食材から使う「先入先出」の徹底
・在庫管理表の作成または在庫管理システムの導入
・定期的な棚卸しによる在庫数や賞味期限のチェック
・仕入れた食材に入庫日・賞味期限などの日付関係を記載
・食材の正しい温度管理(冷蔵・冷凍・常温など)や保管方法の周知 など
こちらの記事も参考にしてみてください。
毎日の売上分析ならPOSレジ「ユビレジ」のご利用を
飲食店における利益率は、売上高-売上原価(原材料費)-販管費で算出する営業利益を、売上高で除すことで算出します。利益率は原材料費・人件費・広告費の見直しや販売計画の策定・改善など、経営分析に利用できる重要な指標です。
しかし1日に何十~何百人単位の集客を行う飲食店において、料理・サービスごとの売上高や売上原価を確認するのは多大な労力が必要となります。
会計データを記録しつつ売上分析をしたいなら、弊社のPOSレジ「ユビレジ」導入をご検討ください。ユビレジなら期間や商品ごとの売上管理・分析から、原価・勤怠・予実管理などの経営管理まで幅広く対応できます。またユビレジ在庫管理も同時に契約することで、商品在庫管理や棚卸データの入力も可能です。
▼飲食店経営についておすすめの記事
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。