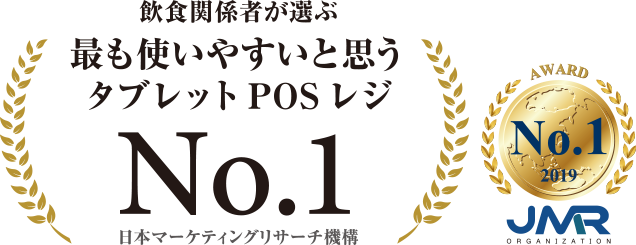労働環境やコロナ禍の影響で人材採用は難しくなっており、定着率の向上や離職を防ぐ取り組みが重視されています。
特に飲食業界にとって人手不足は慢性的な問題であり、頭を悩ませている経営者の方は多いのではないでしょうか。
今回は、労働環境の改善やシステム導入による効率化など、飲食業界における「人手不足」を解消する方法について詳しく解説するので、人手不足に悩んでいる経営者の方はぜひ参考にしてください。
飲食店の人手不足の現状
近年の飲食店は、ほかの業種と比較して人手が不足している傾向にあります。帝国データバンクの調査によると、2022年10月の時点で非正規社員が不足していると感じている企業の割合は飲食店が最も高いという結果が出ています。
7割以上の飲食店が非正規社員の人手不足を感じており、それにともなって長時間労働も増加。さらなる離職につながる可能性があるため、個別の店舗でも対策が求められています。
このように人手不足解消は飲食店の大きな課題であるといえるでしょう。
【出典】「人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)」(帝国データバンク)
URL:https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p221110.pdf
飲食店が人手不足に陥る原因
飲食店が慢性的な人手不足に悩まされてしまう原因はいくつかあります。ここでは、そのなかで重要な5つの原因について解説をします。
シフトが不規則で働きづらい
第1の原因は、「不規則な勤務だと従業員が働きづらい」ということです。飲食店の場合、営業時間が長いことや定休日が少ないことから、従業員はシフト制の勤務になることも多いでしょう。
しかし、働く人にとっては、勤務する日や時間が不規則になることは、働きづらさを感じる要因にもなりえます。たとえば不規則勤務だとゆっくり体を休められず体調を崩すことになりかねないという不安をもつ人もいるでしょう。
また、従業員にも自身の生活スタイルがあるため、繁忙期などで希望するシフトで勤務できない状況が続くと離職につながる可能性が高まります。
人手不足に陥るとシフトの融通が利きづらくなり、従業員の希望に沿ったシフト管理が難しくなります。それが従業員の離職につながり、より人手不足が深刻化するという悪循環になってしまうのです。したがって、シフトが不規則である場合、離職率が高まるといえます。
農林水産省が公表している「外食・中食産業における働き方の現状」によると、特に非正社員の女性では「残業が多く労働時間が不規則」との回答が33.8%になり、正社員と比べて比率が高くなっています。
【参考】「第4回働く人も企業もいきいき食品産業の働き方改革検討会 外食・中食産業における
働き方の現状と課題について」(農林水産省 食料産業局)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/hatarakikata_shokusan/attach/pdf/04_haifu-11.pdf
長期的に働く人が少ない
第2の原因は「長期間にわたって働く人が少ない」ということです。一般的に飲食店では働き手の入れ替わりが激しいという傾向がみられます。
厚生労働省が公表した「令和2年雇用動向調査結果の概況」によると、宿泊業・飲食サービス業の入職率は26.3%、離職率は26.9%となっています。この数値は宿泊業も含まれてはおりますが、一般的に飲食業界は、入ってくる人より辞める人の方がやや多い状況であると考えられます。
全産業の中でも宿泊業・飲食業は入職率と離職率が一番高く、複数あるサービス業の中でも最も多い割合です。
また、飲食店の働き手はアルバイトやパートなど、非正規で雇用される形態の人が多いようです。安定的に働きたい人向けの雇用形態ではないため、働き手が離職しやすい環境といえます。
【参考】令和2年雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-2/dl/gaikyou.pdf
労働環境に問題がある
第3の原因は、「労働環境に問題がある」という点です。労働環境が思わしくないと、当然従業員は職場に定着しにくくなるでしょう。
飲食店の労働災害は増加傾向にあり、労働環境は必ずしも良好とは限りません。第三次産業のうち飲食店の労働災害は9%を占め、死傷者数も増加しています。
平成28年の飲食店の労働災害では、「転倒災害」が28%を占めており、最も多い割合です。次いで多いのが「切れ・こすれ」23%、「火傷等」などが17%となっています。
たとえば、オーダーのドリンクを取りに行くときに、通路とカウンター前の段差で足を踏み外し転倒しまった場合は「転倒災害」となります。「切れ・こすれ」の例では、右手でピーラーをもち、左手でもった人参の皮をむきながら、話しかけられた方を振り返り、指先を切ってしまうなどのケースが考えられるでしょう。
飲食店は、他の業種に比べてケガをする機会が多いようです。危険や注意すべき事項を「⾒える化」することで、従業員の安全を守ることができます。
【参考】第三次産業の労働災害の特徴(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000211862.pdf
クレーム対応にストレスを感じる
第4の原因は、クレーム対応によって従業員がストレスを感じ、離職につながっているということです。
飲食店は接客業であるため、クレーム対応を必要とする場面が多々あります。クレームのなかでも、特に従業員に非がないカスタマーハラスメントを受けることは、従業員にとって大きなストレスの原因となるでしょう。不当な扱いや迷惑行為を受けることによって抱えた大きなストレスは、従業員の離職につながってしまいます。
感染症拡大の影響で従業員の離職者が増えた
第5の原因は、新型コロナの感染拡大が広がったことで、従業員の離職が増えたということです。新型コロナウイルスの影響による営業規制や休業により、アルバイトの解雇やシフトの削減を余儀なくされた企業は数多くあります。緊急事態宣言や時短要請により、廃業の決断を迫られた飲食店も少なくありません。
現在、新型コロナウイルスによる飲食店の制限は解除されましたが、多くの飲食店は再び従業員を集める必要があります。営業を通常通りに再開しても離職した従業員が戻らず、スタッフが不足するケースが見られ、飲食店は非常に厳しい状況だといえるでしょう。また、新型コロナウイルスが流行する前と比べると、求職者の心境の変化も飲食店の人材不足に追い打ちをかけています。特にテレワークの普及によって場所にとらわれない自由な働き方に注目が集まり、若手の人材は集まりにくくなりつつあります。加えて、感染症への意識が高まり、接客業である飲食店でのバイトを避ける傾向にある点も飲食店が人材不足に陥る原因の1つです。
【関連記事】
人手不足に悩む飲食店が見直したいポイント
飲食店の売上を伸ばすには、必要な働き手をしっかり確保していかなければなりません。ここでは、人手不足に悩む飲食店が見直したいポイントについて解説をします。
従業員の労働条件
1つ目のポイントは、「従業員の労働条件」を見直すことです。従業員が無理のない条件で勤務できているかを確かめます。
見直すポイントは、以下の4点です。
1.十分な休みを確保できているか
2.深夜や早朝にシフトが集中していないか
3.特定の従業員に負荷がかかっていないか、
4.適切な額の給与を支払っているか
厚生労働省が規定している労働時間をオーバーしないように、従業員の休日を確保しなければいけません。深夜や早朝の時間帯に集中して勤務するようなシフトになっていないかも確認しましょう。
そして、仕事ができるからといって特定の従業員に仕事が集中することがないように注意を払ってください。
また、仕事に対するモチベーションを向上させるためには、働きに見合った額の給与が必要です。給与の不満は離職につながるため適切な額の給与を支払うようにします。
上記の点を見直す際は、具体的に以下の項目を改善するとよいでしょう。
勤務日や勤務時間
従業員が勤務日や勤務時間に悩みを抱えやすい職場は、人手不足になりやすい傾向があります。特に従業員のシフトの融通が利きづらいと、働きにくく感じてしまうため注意が必要です。新規従業員の定着率を上げたり、既存従業員の離職を減らしたりするためには、できる限り従業員の希望に沿った勤務日や勤務時間で働いてもらうことが大切です。また、シフトを作る際は希望に沿った十分な休みが確保できているか、深夜や早朝といった体力的に負担の大きい時間帯にシフトが集中していないかなどを重要視しましょう。希望する日程や時間での勤務がしやすければ、従業員は働きやすく感じて離職率が減り、人手不足になりにくくなります。
給料や評価制度
給与は従業員の働くモチベーションを左右する大きな要因の1つです。従業員の働きを正しく評価して適切な金額の給与を支払えば、離職率の低下に大きくつながります。評価制度を設けて報酬の水準を明確にすれば、既存の従業員は給与アップを目指し、モチベーションが大きく向上するでしょう。また、給与水準が明確であることで不明瞭な点がなくなり、求職者が集まりやすい効果も期待できます。
職場環境や教育制度
職場環境や教育制度は、従業員の働きやすさに大きく影響します。そのため、人材不足を防ぎたいのであれば、求職者や既存の従業員にとって魅力的な職場であるかどうかを見直さなければいけません。職場環境に関しては、業務量や仕事内容、人間関係、職場の衛生状態などに問題がないかの確認が必要です。
また、教育制度に関しては、仕事の内容を正しく伝えられる環境であるかを確認しましょう。人材を確保するためには、従業員が働きたいと思える労働環境を提供することが大切です。
従業員とのコミュニケーション
2つ目のポイントは、「従業員とのコミュニケーション」を大切にすることです。職場のコミュニケーションは労働環境に大きく影響するものであり、働く人同士が気軽にコミュニケーションを取れる環境であると、職場の雰囲気が楽しくなります。
したがって、パワハラなどはもってのほかです。経営者や上司の立場である人が過剰に従業員を怒鳴ったり、執拗に叱ったりすることが多いと、当事者である従業員だけでなく、その場面をみている従業員もストレスを感じやすくなり離職願望が出てきます。
飲食店の経営者や管理職は、風通しがよく、従業員一人ひとりを大切にするホワイト企業を目指すことが必要です。そのためには、従業員や部下の意見を尊重することも心がけましょう。
採用戦略
3つ目のポイントは、「採用戦略」をきちんと立てることです。新規採用がうまくいかないときは、募集の仕方に問題があるのかもしれません。採用戦略を見直すとよいでしょう。
重要なのは求人情報をできるだけ具体的にすることです。どのような仕事内容なのかを明確かつ分かりやすく記載することで、求職者がイメージをつかみやすくなります。
「飲食店で働く=ハードな勤務」というイメージを払拭することにも配慮しましょう。勤務に対するハードルを下げると求職者の増加につながる可能性があります。
たとえば、「シフトを短くする」「未経験者でも働ける仕組みを作る」 といった取り組みを行い、長時間勤務に不安がある方や未経験の方でも応募しやすい条件を整えれば、求職者の数が増えることが期待できます。
飲食店の人手不足を解消するアイデア
人手不足の場合は、何か手を打たなければ、いつまで経っても問題は解消しません。ここでは、飲食店の人手不足を解消するアイデアをご紹介します。
労働環境や待遇を改善する
飲食店の人手不足問題を解決する方策のひとつは、離職者を極力なくすことです。そのためには、働く人の意見を積極的にとりいれていく仕組みを作ることもポイントです。
たとえば、定期的にヒアリングをおこない、従業員の会社に対する要望や仕事の悩みなどを拾い上げるといった取り組みも効果的でしょう。これによって明確になった事項に的確に対応していくことが、従業員が継続して働きたいと望む理由になる、「やりがいのある仕事」「働きやすい職場」の実現につながります。
店舗運営を見直す
新型コロナ感染拡大の影響により、飲食店の経営は依然として厳しい状況が続いています。それに応じて、少ない従業員で運営できる体制を考えるといった店舗運営の見直しが必要になってきているのではないでしょうか。実際、総務省統計からは、外食業界は雇用を多く生むが稼ぐ力が低いという状況も見て取れます。この機会に店舗運営を見直してみましょう。
たとえば、今まで常態化していた作業で無駄なものはないか、さらに効率良くできる方法はいかなどを考えます。中小企業診断士などに企業の成長戦略策定やその実行のためのアドバイスをもらってもよいでしょう。
社内で現在行われている作業のチェックシートを作り、従業員全員で確認するのもよい方法です。
業務を効率化するシステムを導入する
たとえば、今まで常態化していた作業で無駄なものはないか、機械の導入で人の負担を減らして自動化できる作業はあるかなどを再確認します。
近年のIT技術の進化に伴い、飲食店でもデジタルトランスフォーメーション(DX)にむけて取り組むところが増えてきました。自動化することでヒューマンエラーを減らせる効果もあり、営業の効率があがります。
飲食店は人に対するサービス業ということもあり、テクノロジーに対して苦手意識を持っている方も多いかもしれません。しかし、近年のDXは飲食店においてもさまざまなサービスを提供できるようになり、業務を効率化するシステムを導入することは、もはや欠かせない要素といえるでしょう。
実際、サービス業務のDXに取り組む飲食店は増えています。昨今増えてきているスマホやタブレットによるセルフオーダーシステムを用意すれば、わざわざオーダーをとるために従業員がお客様の席まで行く必要はありません。それによって少ない人数で業務が可能になるため、人件費の削減が期待でき、ひいては業績アップにも役立つと考えられます。
こちらの記事も参考にしてみてください。
採用条件を変更する
人手不足である原因の1つとして、採用条件が魅力的ではないからといった点が挙げられるでしょう。求人の内容を見直し、より魅力的な採用条件に変更すれば、求人からの応募数増加が期待できます。人件費の増加は店舗経営にとってデメリットとなりますが、特に時給が見直せないかは、必ず検討しましょう。
また、近年は働きやすさも重要視されるため、職場の魅力的なポイントも積極的にアピールすることも効果的です。
採用の幅を広げる
外国人やシニア層など、採用を希望する人材の幅を積極的に広げると応募数が増加します。近年では、人手不足を解消するために外国人やシニアの採用に力を入れている企業も数多く見られます。
ただし、外国人を雇用する場合は、在留資格などの制度や雇用条件が異なるため注意が必要です。制度や条件については必ず事前に確認をしましょう。
そのほか人手不足を解消するアイデアとしては、以下の記事で紹介している方法も参考になります。
飲食店の人手不足には経営戦略の見直しが必要
「人手不足を解消するための経営戦略として注目したいのが集客システムの導入です。そのひとつが「ユビレジQRオーダー&決済」です。
「ユビレジQRオーダー&決済」はお客様が自分のスマホで好きなタイミングにオーダー・支払い(クレジット決済)できる便利なシステムです。オーダーや支払い時に従業員に声をかける必要がないため、ストレスなく食事の時間を楽しめます。
また、飲食店にとっては従業員オーダーをとる時間を削減できるため、その他のサービスに時間がかけられるようになります。ぜひ、この機会に便利なオーダー&決済システム「ユビレジQRオーダー&決済」を導入されてはいかがでしょう。お店の業務効率化が図れます