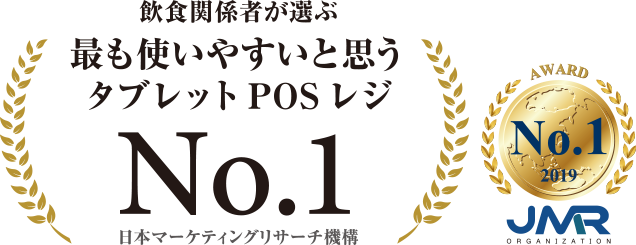飲食店開業の際に乗り越えなければならない壁の一つが「店舗コンセプト決め」です。カフェ、ラーメン屋、カレー屋、中華料理屋、バー、居酒屋、和食屋など「何を扱うお店か」は決めたものの、どんなお店にすれば成功できるのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
コンセプト作りは開業準備の第一歩です。お店の魅力そのものであり、事業の成功に大きな影響を及ぼします。必ず成功するコンセプトの決め方は、残念ながらありません。しかし、なるべく失敗しないように注意点を意識しながらコンセプトを考えていくことは大切です。
「飲食店の独立・開業・経営のための15の準備」でも簡単に説明しましたが、このコラムでは飲食店にコンセプトが必要な理由や有名な人気店の事例、コンセプト作りのポイントなどをより深く解説していきます。
コンセプトはすぐに出来上がるものとは限りません。何度も試行錯誤を重ね、最高のコンセプトを作り上げましょう。
飲食店にコンセプトが必要な理由と注意点

コンセプトは店名や店舗デザイン、業態などに関わる重要な要素です。コンセプトを決めるメリットはいくつもありますが、必ず設定する必要はあるのでしょうか?以下でコンセプト設計における注意点とともに解説します。
コンセプトを決める理由
コンセプトとは、お店の「テーマ」や「骨子」のことです。簡単に言うと「どんな飲食店にするか」ということであり、お店がお客さんに提供する価値を表します。
創業時、絶対にコンセプトを決めなければならないというわけではありません。ただし、コンセプトがなければお店の方針についての軸も決まらず、一貫性のない状態に陥ってしまうことがあります。考え方の軸を作り、お店を開店する際の迷走を防ぐためにも、コンセプトを決めることは重要です。
お店を開店するにあたっては、以下で挙げる例のように決めるべきポイントがあります。
- 店名
- 立地
- 内装
- 価格
- 開店時間
- 雇い入れる従業員
こうしたお店の詳細を決める際に、考え方の軸が決まっていれば、方針で迷走した時やアイデアが出ない時などに悩まなくて済むでしょう。
「こういうコンセプトなら、この店名のほうがお客さんにわかりやすいな」
「このコンセプトを伝えるためには、こんな内装が必要だな」
「このコンセプトに共感してくれる人を雇おう」
といった具合で結論を出すことが可能です。
ほかにも、コップのデザインやPOPのメッセージといった店舗運営に必要なちょっとしたことでも、コンセプトに沿って決めればよくなります。逆に軸がないと、結果としてちぐはぐなお店となってしまい、お客様に価値を十分に伝えられず失敗することになりかねません。
成功しているお店には、しっかりとしたコンセプトがあるといわれています。お客様が「このお店に行けば、こういう価値を提供してくれる」ということが明確にわかるため、お店のブランディングも行いやすい点がメリットの一つです。また、コンセプトに沿った店づくりをすればお客様にも魅力が伝わりやすくなります。「こんなお店に行った」という口コミも広まりやすく、集客やリピーター獲得にもつながるでしょう。
コンセプトを決める際の注意点
飲食店開業を検討している場合、すでに「こんな業態のお店をやろう」というアイディアがあるかもしれません。例えば、「伝統的な赤酢を使った江戸前寿司を提供しよう」「ハワイに精通したスタッフを集めた店舗を作ろう」など、具体的なイメージを描いている方も多いのではないでしょうか。
こういったアイディアは、コンセプトを決める上で重要な材料となりますが、コンセプト自体とは区別して考える必要があります。ここでいう「アイディア」とは「お店が提供することができる商品・サービス」で、コンセプトは、そこから一歩踏み込んで「お客様が実際にお店に訪れたくなる理由」です。一度アイディアとコンセプトを区別して考えてみましょう。
有名飲食店のコンセプト事例

コンセプトを決めたいものの、具体的な案が思いつかないという方もいるかもしれません。その際は、実際に使われているコンセプトを参考にしてみましょう。こちらでは、有名店の例をご紹介します。
スターバックスコーヒー
コンセプト:Third place(第3の場所)
世界的に愛されているカフェであるスターバックスのコンセプトはとてもシンプルです。第1の場所である「家庭」、第2の場所である「職場・学校」の次に位置する、人々が交流する場所としての「第3の場所」となることをコンセプトに店舗展開をしています。このコンセプトをもとに「居心地のよい店」「集いやすい立地」などを店舗設計し、従業員にも徹底させることで支持を得ているのです。
いきなり!ステーキ
コンセプト:本格ステーキを立ち食いで量り売り
ステーキといえば「高級」で、レストランの座席に座ってじっくりと味わうというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。いきなり!ステーキは、高級さとは真逆の「立ち食い」「量り売り」でステーキを提供するという、意外な組み合わせでコンセプトを作り上げました。ターゲット顧客にこれまでにない価値を提供することで大成功を収めている例です。
吉野家
コンセプト:うまい、やすい、はやい
飲食店のコンセプトの中でも広く知られているのが吉野家の「うまい、やすい、はやい」というフレーズではないでしょうか。美味しい牛丼を低価格で素早く提供するという、ファストフードとしての強みがはっきりとわかります。想定するターゲットに訴求しやすいことも特徴です。
スシロー
コンセプト:うまいすしを、腹一杯
大規模回転寿司チェーンの一つであるスシローのコンセプトです。高い品質のお寿司を安価に提供する、という方針を最大限に表現しています。シンプルでありながらインパクトがあり、顧客に伝わりやすいコンセプトといえるでしょう。
鳥貴族
コンセプト:319円均一(税抜)の感動
安くて美味しい焼鳥屋さんとして、たびたびメディアにも取り上げられている鳥貴族のコンセプトは、金額が明確に出ている点が大きな特徴です。「安価でありながらお客様に感動してもらえるような商品を提供したい」という企業の思いが、具体的な価格とともに表れています。
コメダ珈琲
コンセプト:「誰もがくつろげる『街のリビングルーム』」
美味しいコーヒーやスイーツ、食事などを提供しているコメダ珈琲では、居心地の良い、くつろげる空間づくりを大事にしています。このコンセプトは店内空間にも表れており、ソファの色味やテーブルの厚みなど、細かい部分にまでこだわりが見られます。
Soup Stock Tokyo(スープストックトーキョー)
コンセプト:「食べるスープ」
Soup Stock Tokyoは、理念として「世の中の体温を上げる」を掲げています。キャッチコピーの「いつでも、誰にでも、おいしいスープを。」からもわかるように、全てイメージが一貫していてメッセージが伝わりやすい点が魅力です。
シンプルだと強いが、規模によってはもう少し具体的にしてもよい
ご紹介したものはいずれも大規模チェーンの事例です。非常にシンプルであり、抽象的に見えるものも少なくありません。ただ、いずれもそのコンセプトに忠実に店舗づくりをしているからこそ、根強いファンが付き、繁盛店となり成功を遂げています。規模の小さいお店では、ここまでシンプルなコンセプトで進めることは難しいかもしれませんが、これらのコンセプトを参考にしてみるとよいでしょう。
【コンセプトの決め方 STEP1】アイディアを見つける

実際にコンセプトを決める際に、まず必要なのはアイディアです。アイディアは競合店の情報やトレンド情報から考えることができます。すでにお店で提供したい価値が決まっていれば、そこからコンセプトを作ることもできるでしょう。
また、アイディアのヒントは、7W2Hの視点から探すと見つけやすくなります。コンセプトで悩んでいる方は、これからお伝えするアイディアの見つけ方に沿って考えることもおすすめです。
アイディアを身近なところから見つける
ここからは、具体的にどうやってコンセプトを作り、使っていくかをステップごとに説明していきます。まず、新しく始める自分のお店でどんなことをしたいか、すでにお持ちのアイディアはあるでしょうか。もしあるのであれば、そのアイディアをもとにコンセプトを考えても良いでしょう。その上で、ほかにも有望なアイディアがないか調べてみることがおすすめです。
- 自分が欲しいもの
- 雑誌やテレビ番組、インターネットなどから得られるトレンドの観察
- 取引先からの情報
- 競合店の動向
などで、有望そうなアイディアのヒントがなかったか、考えてみましょう。アイディアは多ければ多いほど良いといえます。たくさんの候補から一番有望そうなものを選ぶこともできますし、すでにあるアイディアとかけあわせることで、より発展させたものが見つかるかもしれません。
コンセプトに悩んでいる段階であれば、やり直しには苦労もありません。自分が納得できるアイディアを探し続けましょう。
7W2Hからアイディアのヒントを見つける
なかなか良いアイディアが出ない場合、「5W1H」ならぬ「7W2H」をもとに、お客様に提供できるコンセプトの素や「こだわり」を考えてみましょう。
「5W1H」とは、英語の勉強でよく使われる以下の単語を指します。
- When
- Where
- Who
- What
- Why
- How
さらに、次の3つを足したものが「7W2H」です。
- Which
- Whom
- How much
これらをもとに、自分に質問を重ねてアイディアを出していくのです。
| When(いつ) | 開業時期は? |
| Where(どこで) | 出店場所は?どのような立地? |
| Who(誰が) | どのようなスタッフと? |
| What(何を) | どのようなメニューを提供しますか? |
| Why(なぜ) | なぜあなたはそのお店を開業したいのですか? |
| How(どんなふうに) | お店のコンセプトはなんですか?内装のイメージは? |
| Which(どれを) | 特におすすめしていきたいメニューや商品はなんですか? |
| Whom(誰を) | メインターゲットとする客層は? |
| How much? (いくらで) | いくらで提供しますか? |
【When……いつ】
開業しようとしている時期について考えます。なぜその時期にお店を始めるのか見つめ直してみましょう。
【Where……どこで】
開業したい場所、開業できる場所を考えます。そこはどんな街で、どんな人が来るのかを確かめてみましょう。高級住宅街やオフィス街、地方の商店街など、エリアの特徴を調べることも重要です。
そうした場所に沿ったコンセプトを考えてもいいでしょう。あるいは、エリア内の競合店が実践していないコンセプトをあえて狙ってみるのもいいかもしれません。
【Who……誰が】
お店で働く人のことを考えます。飲食店の場合、他店とメニューが被ってしまうことは珍しくありません。ただ、働く人は一人ひとり違います。出身地や性格、経歴、醸し出す雰囲気などもさまざまです。そこに、お店が打ち出すべきコンセプトのヒントがあるかもしれません。
【What……何を】
お店提供するメニューは何かを考えます。料理の種類だけでなく、産地や農法、製法、鮮度など、こだわりたいものや、他店にはないものなどをイメージしていきましょう。
【Why……なぜ】
お店を始める理由を考えます。なぜお店を始めたいのか、なぜそのメニューを作るのかといった根本的な理由から生まれるコンセプトもあります。例えば「ラーメンが好きだから」「イタリアンを修行したから」という理由で開業する場合、さらに突き詰めてみましょう。「なぜラーメンが好きなのか」「なぜイタリアンを修行したのか」と問いかけを繰り返して行く中で、自分だけが提供できる価値を見つけられるかもしれません。
【How……どんな風に提供するか】
料理をどのような空間でどのように提供するかを考えます。同じ料理でも、提供される方法や空間によって、お客様が得る体験は全く違ってくるでしょう。
料理の提供方法には、食べ放題や立ち食い、セルフサービス、テイクアウトなどがあります。お店の空間も、古民家風のレトロな内装や、モノトーンのシンプルな空間など、さまざまなタイプが考えられます。お客様の興味を引くやり方を考えてみましょう。
【Which……どれを】
特におすすめしたいメニューを考えます。数あるメニューの中で、どのメニューを看板メニューにするか考えてみるのも良いでしょう。また、豊富なメニューを取り揃えるのか、反対にメニューを絞って勝負するのかを考えてみることも大切です。
【Whom……誰を】
ターゲットとしたい客層を考えます。お客様になって欲しい人は、どんな人でしょうか。ビジネスパーソン・学生・女性・男性・家族連れ・富裕層・お洒落に敏感な人・音楽好きな人・観光客など、多彩なパターンが考えられます。来て欲しい人が喜んでくれるコンセプトを考えてみるのも良いでしょう。
【How much……いくらで】
料理をどのくらいの価格で提供するのかを考えます。コンセプトにおいて、価格帯や値段自体を前面に出すことも可能です。競合店よりも安く提供するのか、あるいは付加価値を加えて高くするのか、といったところからコンセプトを整えてみましょう。
【コンセプトの決め方 STEP2】一言で言えるキャッチフレーズに落とし込む
コンセプトに関するアイディアを思いついたらどんどん書き出していくことが大切です。箇条書きでも文章でもかまいません。次に、そうして出てきたアイディアを組み合わせたり、突き詰めたりしてみましょう。
重要なのはそれが「お客様がお店に来る理由になるか?」です。決して独りよがりにならず、お客様の立場になって、行ってみたくなるコンセプトかどうかを考えてみましょう。
また、コンセプトは、誰にでもすぐにわかるものである必要があります。箇条書きやだらだらと長い文章では他人に伝えることが難しく、自分でも理解しにくいものです。コンセプトを決めたら、一言で表現できるようなキャッチフレーズに落とし込んでみましょう。パッと聞いてお店のイメージが湧くよう、なるべく余計な要素をそぎ落として端的に表してみることがコツです。
【コンセプトの決め方 STEP3】コンセプトシートをつくり、具体的な店舗をイメージする
コンセプトの価値は、実際にお店がオープンして、サービス・商品がお客様に届くことで初めて生まれます。コンセプトが決まったらもう少し具体的な要素に落とし込んで考えてみて、自分の理想とするお店にふさわしいか見直してみましょう。その際は、お店の根幹となる次の8つの項目を書き出しながら、コンセプト設計をしていくことがおすすめです。
順番通りに記載することで状況を整理しやすくなりますが、書きやすいところから書いても良いでしょう。重要なのは「基本コンセプト」とズレがないかということです。常にこの基本コンセプトを意識して、書き出してみましょう。
もし、各項目内容と基本コンセプトが相反するようであれば、どちらかを見直さなければならないかもしれません。ここでは、コンセプトシートの作り方や各項目について解説します。
1. 立地・物件条件
お客様が直接足を運ばなければならない飲食店にとって、どういう場所で店舗経営を行うかは非常に重要です。一般的には駅の近くなど、交通量が多くアクセスが良い場所が有利です。しかしこういった条件の良い場所にお店を出せるとは限りません。隠れ家的なお店であれば、かえってある程度アクセスが悪いほうが、雰囲気に合っているといえるでしょう。
また、物件の広さも大切です。広いほど多くの席をつくれる上、ゆったりしたレイアウトにできます。しかしそのぶん管理が大変になり、賃料も高くなります。
お客様の立場で考えてみると、基本的にはいつも通勤や通学などで移動する範囲の中から、目的を満たすお店を探すはずです。例えば、設定しようとしている営業時間内にお店の前を通る人はどんな人でしょうか?通勤する会社員が多いのであれば、朝食の需要があるかもしれません。
2. ターゲット
ターゲットとは「誰を顧客とするか」ということです。「誰からも愛される」というのは一つの理想ですが、現実的にはお店を訪れる顧客は限定されるものです。どんな人がお店に訪れるのか、漠然とイメージがあるかもしれませんが、きちんと整理してお店の強みは何になるのかを考えてみましょう。
想定しておきたいターゲットの条件は以下の通りです。
- 年齢、性別
- 収入
- 職業
- 家族構成
- 来店する時間
例えば、高級料亭と気軽に入れる定食屋を比べると、主にターゲットの収入が違ってきます。牛丼屋を考えてみても、個人客に集中するのかファミリー層も重視するのかという選択肢があります。自店舗のコンセプトに上手くマッチするのはどのようなターゲットかを突き詰めていきましょう。
3. ポジショニング・利用動機とメリット
ポジショニングとは、お店がお客様にとってどういう位置づけなのかということです。お客様が何のために来店するのか、利用シーンを考えてみると、わかりやすいかもしれません。
- 毎日利用する定食屋なのか、接待に使う料亭なのか
- デートで訪れるお店なのか、友人と楽しく酒を飲むために訪れるお店なのか
- プレゼントを購入するのか、普段使いのものを購入するのか など
位置づけは他のお店と比較することでも明らかになるものです。開業する予定の店舗は他の店舗とどう違うのか、考えてみましょう。
4. サービス・オペレーション
接客スタイルもコンセプトに沿って考えてみましょう。お客様をどんな風にお迎えして、どんな風にメニューをお知らせして、注文を受けるのでしょうか。お料理の提供はセルフサービスでしょうか。それとも一品ずつお届けするのでしょうか。目の前で取り分けてくれるのでしょうか。お客様自身に取り分けていただくのでしょうか。
また、コミュニケーションの部分についてもイメージしましょう。商品知識を豊富に持つスタッフが接客し、お客様とおしゃべりをしながらじっくり決めてもらうのでしょうか。モバイルオーダーなどを活用して、ほとんど対話することなく会計まで進んでもらうのでしょうか。もし人を雇って接客してもらうとしたら、提供したいサービスに適した人材を探す必要があります。
5. メニュー
飲食店において重要なのはメニューです。安心できる定番メニューもあれば、そのお店でしか提供できない料理やお酒もあるでしょう。
品目数を多くし選択肢を増やすか、少数精鋭のわかりやすいメニューとするかを決定します。「売り」となる看板メニューを考案することも、成功の秘訣です。ターゲットの客層や提供するメニューから、客単価も想定しておきましょう。
6. 店内外環境
内装・外装の店舗デザインやメニューブックのデザイン、POPデザイン、食器、調度品など、お客様が実際に見て触れる環境は、お店で得られる体験の大部分を占める重要な要素です。とはいえ、店内外の環境整備は、開店時にかかるコストの多くを占める部分でもあります。開業資金の金額次第では特に大事な要素に絞ってお金をかける必要があるでしょう。コンセプトが伝わり、お客様に満足していただけるような環境とはどんなものなのか、じっくり考えることが大切です。
7. 価格・支払い方法の設定
メニューの価格は商品の原価や人件費、家賃などの影響を受けますが、オーナー自身で設定することができます。しかし、お客様が価格に納得しなければ注文数は増えません。料理や商品、サービスの品質に見合った料金である必要があります。価格が高い場合には高い品質が求められることもあるのです。
また、支払い方法は、お客様の利便性に関わる部分です。クレジットカードや各種電子マネーなどを利用しての支払いができると、便利だと感じてもらいやすいでしょう。ターゲット客層に合わせて柔軟な支払い方法を検討することが大切です。
8. プロモーション
良いお店をつくれたとしても、その存在を知らない人が訪れることはありません。プロモーションを実施してお店の存在を周知することが大切です。お客様がお店を訪れたくなる理由をアピールしましょう。
雑誌などの紙媒体への広告掲載、割引クーポンの配付、インターネット、看板など、プロモーションにはいろいろな方法があります。お店のターゲットにどのくらい効果があるかを考えて適切な方法を選びましょう。
【関連記事】
【コンセプトの決め方 STEP4】満足のゆくコンセプトにたどり着くまで繰り返す
お店のコンセプトが大まかに定まったら、いったん見直してブラッシュアップしていくことも大切です。納得のいくコンセプトになるまで吟味を続けていきましょう。
コンセプトを見直すときのポイント
コンセプトを決めた際は、そのまま最終決定するのではなく、事業として実現できるコンセプトかを確認することが大切です。理想とするコンセプトと現実が離れていないか見直してみましょう。コンセプトに込めたメッセージは伝わりやすいか、コンセプトシートに書き出した内容に矛盾はないかなどをチェックします。コンセプトを読んで理解しやすい内容か見直しましょう。コンセプトが実現不可能と判断した場合や、違和感を覚えた場合などは、再検討したほうが良いかもしれません。
自分で判断するのが難しい場合は他の人にチェックしてもらっても良いでしょう。成功している飲食店経営者やアドバイザーなど、専門的な知識のある人に伝手がある場合はアドバイスをもらうことがおすすめです。ターゲット層に近い属性を持つ友人・知人などに見てもらっても良いでしょう。
コンセプト通りのお店を実現するために
思い描いたコンセプト通りのお店が実現できればすばらしいことですが、常にそう上手くいくとは限りません。「理想的な物件を見つけたがすでに入居するテナントが決まっていた」「目玉となるこだわり食材が予想よりも高コストだった」など、コンセプト通りに進められないことは珍しくありません。コンセプトよりも先に店舗の場所が決まっているケースもあるでしょう。
実情とコンセプトがそぐわない場合は再検討を行います。このときに大切なのは、最初から考え直すことです。変える必要のない部分はそのままでかまいませんが、変更によって何かのバランスが崩れていないか確認しましょう。
例えば、出店するエリアを変更することになったのであれば、他をそのままにするのではなく、ターゲットからプロモーションまで全部を見直します。もしかしたらアイディアそのものにも変更が必要かもしれません。
飲食店のコンセプトに合う内装やメニューの考え方
これまでご紹介してきた方法も参考にコンセプトを決定できたら、内装やメニューなどに反映させましょう。コンセプトからテーマ性や雰囲気を設定することで、店舗づくりに活かすことができます。
内装の全体的なカラーコーディネートや家具・設備、照明などはコンセプトに合わせて設計します。お客様がじっくり眺めることになるメニューデザインにもこだわりましょう。
メニューを作る際にはターゲット層に合わせた内容になるよう構築することも重要です。その際は7W2Hのアイディアやコンセプトシートを活用しましょう。ターゲットやコンセプトがしっかり定義されているため、迷わずメニュー作成を行いやすくなります。
飲食店のコンセプトを決めるメリットと運営後に気にかけたいこと
これまでご紹介したように、飲食店の運営においてコンセプトの決定は非常に重要です。コンセプトを決めることで、差別化や経営面でもメリットが得られます。一方で、開店後も運営内容や接客がコンセプトと合っているか気にかける必要があるでしょう。
コンセプトを決めるメリット
コンセプトに沿って決めるためお店に関わる判断が早い
コンセプトに沿って物事を決めれば、お店の重要な判断がスムーズに進みやすくなります。特に新規開店のお店だと、家具のデザインやメニューの金額、仕入先など、どのように決めれば良いかを判断するのが難しいものです。コンセプトがあれば1つの判断基準が作れるため、選択肢が広がりすぎずに効率の良い意思決定ができるようになります。
競合店との差別化
コンセプトの決定は、競合店との差別化においても重要です。例えば、競合店と自店舗が同じラーメン屋の場合、「早い提供スピード」や「高いコストパフォーマンス」などがコンセプトとして決められます。競合店よりも優れているポイントを前面に出すことで、自分の店を選んでもらえる可能性が高くなるでしょう。
融資が通りやすい
融資を受ける際は、事業内容だけではなく、事業の目的や方針も重要視されます。コンセプトを決めて伝えれば、事業の方向性がある程度わかるため、金融機関は融資しやすくなります。反対にコンセプトのない事業だと、経営の方向性が見えずに信用が得られないため、融資の審査に通らない可能性も高くなるかもしれません。
運営後に気にかけたいこと
コンセプトと運営内容に違いが出てきていないか
長期間運営していると、最初に設定したコンセプトと現在の運営内容にズレが生じる可能性があります。例えば、お客様が増えない、売り上げが上がらないなどの状況になったときはコンセプトと現実が離れている状況といえます。
最初に設定したコンセプトから離れないようにするためには、運営内容を定期的に見直すことが重要です。コンセプトを見失って運営すると軸がブレた運営となり、お客様に不信感を与えることもあるでしょう。そうならないためにも7W2Hやターゲット層の見直しを行い、コンセプトを作り直す必要があります。これに伴い、メニューやお店の雰囲気を変える必要も生じるでしょう。
従業員の接客がコンセプトと合っているか
お店の外装や内装、メニューのほか、接客対応も重要なコンセプトの一部です。料理やお店の雰囲気がコンセプト通りであっても、接客がコンセプトに合っていなければ、お客様には違和感が残ります。
飲食店では従業員の入れ替わりが激しくなることもあります。従業員がコンセプトを深く理解するためには、接客マニュアルの作成や言葉遣いのアドバイスなどが必要です。
コンセプトの運営が顧客目線であるか
飲食店経営を成功させるためには、顧客目線を持ちながら運営することも求められます。お客様の立場に寄り添ったコンセプトが作れていない場合、売上が上がらないなどの問題に陥るケースもあるでしょう。ターゲット層に効果的に訴求し、親しみを持ってもらうためにも、相手の目線に立ってコンセプトを考えることが大切です。
お客様の興味を引くコンセプトを定めて長く愛される飲食店に!
コンセプトとはお店の魅力そのものであり、お客様が訪れる理由になるものです。明快で整合性のとれたコンセプトを作り上げることでお店の魅力はよりはっきりと伝わり、長く愛されることにつながります。差別化や融資などの面でもメリットがありますが、開店後もコンセプトと運営の整合性を考えるなどの注意点もあります。コンセプトを頻繁に変えるのも良くはありませんが、店舗の状況に応じて柔軟に変更していくことは大切です。浮かんだアイディアをもとに最高のコンセプトを作り、運営内容に反映させることで最高のお店を実現しましょう。
コンセプトを決める意義は?
成功しているお店には、必ずしっかりとしたコンセプトがあります。
お客様が「このお店に行けば、こういう価値を提供してくれる」ということが明確に分かるのでリピーターになりやすいのです。またコンセプトに沿ったお店づくりをすればお客様にも伝わるので、「こんなお店に行った」という口コミがされやすくなり、集客にもつながって行くのです。
コンセプトを決めるために最初にやることは?
「7W2H」をもとに、お客様に提供できるコンセプトの素やあなたの「こだわり」を考えてみましょう。