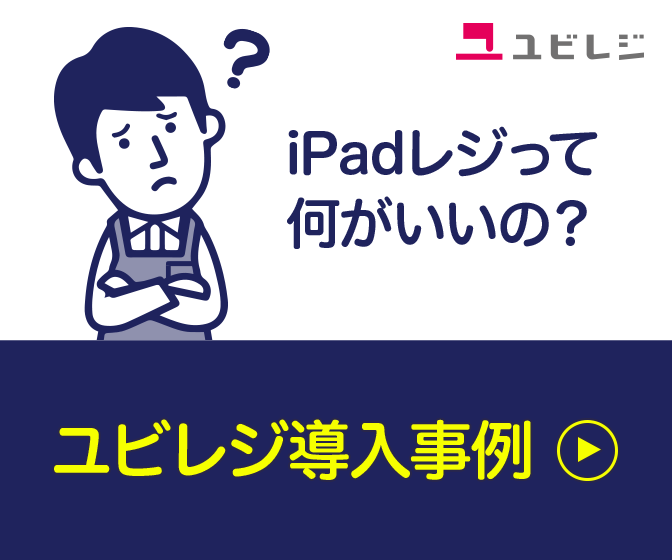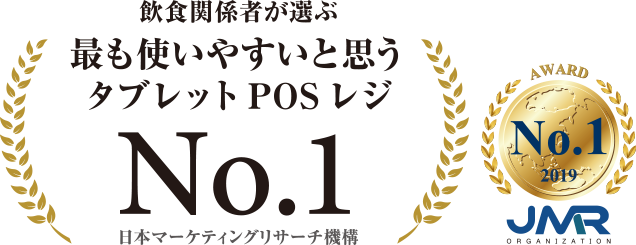「疲れがたまっているから肉でスタミナをつけよう」などといいますが、肉は摂りようによっては逆効果になります。また、疲労の原因物質は運動するときに生成される「乳酸」といわれてきましたが、それも誤りであることが明らかになりました。
そこで今回は、疲労のメカニズムと疲労回復・予防に効く食べ物についての最新情報をお伝えします。
疲労には3種類ある

疲労というのは、心身に受ける外的刺激(ストレス)が長く続くことにより本来の機能が低下する現象で、「肉体的疲労」「精神的疲労」「神経的疲労」の3つに分類されます。それぞれの要因となるストレスをあげてみましょう。
肉体的疲労
環境や生活習慣などにより肉体は疲労を感じます。具体的には、暑さ、寒さ、低気圧、高気圧、騒音、長距離通勤、長時間労働、睡眠不足、運動不足、不規則な生活、栄養不良、過食、偏食、病気やケガ、事故など。なお、病気やケガは肉体的ストレスですが、健康の喪失という点で精神的ストレスにも加えられます。
精神的疲労
人生のさまざまな出来事から起因するストレスにより、精神は疲労を感じます。具体的には、就職、転職、昇進、左遷、失業、退職、残業、夜勤、人間関係のトラブル、結婚、出産、離婚、引越し、大切な人との離別・死別、将来への不安など。マイナスの出来事だけでなく、昇進や結婚、出産などの喜ばしい出来事でも、環境が変化することでストレスになる場合があるのです。
神経的疲労
長時間のデスクワークや、パソコンなどを至近距離で見続けることがストレスとなり、神経を疲労させます。神経的疲労は、脳の疲労とも呼ばれています。つまり、近くを見る作業をしたときに感じる目の疲れは、脳の疲れであるのです。
普通に社会生活を送っていれば、だれでもこうしたストレスに直面することになります。しかし、もともと人間にはストレスから身を守る機能が備わっているので、過度に心配をする必要はありません。
たとえば、人間には暑くなると汗をかくことで体温を下げ、暑さに体を適応させようとします。暑くなったら汗をかくよう、人間の汗腺をコントロールするのが自律神経です。ところが、強いストレスが長期間続くと自律神経のバランスが崩れてしまい、暑くなくても汗が出たり、めまいや耳鳴りなどの症状が現れるようになります。疲労感や倦怠感などの精神症状が現れるのも、自律神経のコントロール機能が低下していることを示しています。
疲労回復物質とは?

疲労回復の食べ物を知る前に、疲労の原因となる物質と疲労回復に効く物質を頭にいれておきましょう。
疲労の原因物質
これまでは疲労感をもたらす直接の原因は、乳酸とされてきました。ところが最近の研究によって、乳酸はエネルギーとして使われる物質であることがわかり、本当の疲労物質はFF(ファティーグ・ファクター)というタンパク質であることが解明されました。
このFFの生成にかかわっているのが、活性酸素と見られています。活性酸素とは、本来ならば免疫や解毒作用のある有益な物質なのですが、大量に発生すると細胞を酸化させる(傷つける)有害物質となってしまいます。
ハードな運動をしたり、過度のストレスがかかったりすると、筋肉や自律神経の細胞で活性酸素が大量発生します。こうして細胞が酸化ストレス状態になるとFFが発生し、その情報が脳に伝わって疲労感が生じるものと考えられています。
私たちの体はすべて細胞でできていますから、肉体的疲労、精神的疲労、神経的疲労とも発生のメカニズムは同じで、その大元は活性酸素というわけです。
疲労回復物質
体内でFFが増えると、それに呼応するようにFR(ファテイーグ・リカバー)というタンパク質が生成されます。FRとは、活性酸素の大量発生によってダメージを受けた細胞のリカバー(回復)を促す物質のことです。私たち人間が疲れても少し休めば元気になるのは、このFRのおかげです。
日ごろから活性酸素が適度に発生する生活を送っている人は、FFも生成されるけれどFRも作られるため、疲れても早く回復することができます。
FFがほとんど発生しない生活、つまり、刺激のない毎日で活性酸素があまり発生しない状態ではFRも作られないので、FRの生成能力そのものが低下していきます。そのため、何らかの強いストレスを受けたとき、FRの生成が追いつかず、疲れが取れにくい体になってしまいます。
逆に、激しい運動を日課にしている人や、人間関係などでストレスフルの生活を送っている人は、活性酸素が過剰に発生することが要因で起こる動脈硬化や糖尿病、がんなどを引き起こす心配があるため、ライフスタイルを見直すことが先決です。
疲労回復に効く食べ物は?

それでは早速、疲労回復に効く食べ物を見ていきましょう。
疲労の原因は活性酸素ですから、活性酸素の発生を抑えることが一番の疲労対策ということになります。それには、ストレスがかかっても上手に発散したり、ウォーキングなど適度な運動をすることで、よく眠れる環境を整えることが大切です。ここでは、抗酸化作用のある食品と上手な摂り方についてご紹介します。
ビタミンC
細胞の酸化を防ぐ働きをします。また、ストレスが蓄積すると副腎からアドレナリンなどの副腎皮質ホルモンが分泌されますが、このときホルモンの原料としてビタミンCが大量に使われます。ビタミンCが不足していると、ストレスに対する抵抗力が弱まってしまいます。ビタミンCは水に溶けやすく、空気や熱でも壊れやすいので、できるだけ早めに生で食べるようにします。
<ビタミンCを含む食べ物>
いちご、キウイ、グレープフルーツ、レモン、ブロッコリー、小松菜、菜の花、みかん、柿など
ビタミンE
「若返りのビタミン」ともいわれるビタミンEは、細胞膜の酸化を防ぐほか、血管を若々しく保って血行をよくし、冷えや手足のしびれなどを改善する働きもあります。
<ビタミンEを含む食べ物>
ピーナッツ、アーモンド、アボカド、うなぎ、すじこ、はまち、ひまわり油、紅花油など
亜鉛
細胞の酸化を防ぎます。不足すると味覚障害や免疫力の低下などを引き起こします。
<亜鉛を含む食べ物>
牛ひれ肉、牛レバー、カキ、卵、チーズ、納豆、高野豆腐、切干大根、アーモンド、ピーナッツなど
β-カロテン
赤や黄色、橙などの色素成分であるカロテノイドの1種です。β-カロテンは体内に入るとビタミンAに変換されます。強い抗酸化作用のほか、目などの粘膜を保護する働きもあります。
<β-カロテンを含む食べ物>
しそ、もろへいや、にんじん、ほうれん草、パセリ、にら、春菊、あした葉、大根の葉、高菜漬けなど
プロアントシアニジン
ポリフェノールの一種です。抗酸化作用が強く、ビタミンEの50倍あるといわれています。美肌効果や病気予防効果もあります。
<プロアントシアニジンを含む食べ物>
ブルーベリー、ココア、アーモンド、ピスタチオ、クランベリー、ざくろ、赤ワインなど
リコピン
活性酸素を除去する働きがあります。疲労回復効果や、美容効果、アンチエイジング効果もあります。
<リコピンを含む食べ物>
トマト、パプリカ、グレープフルーツ(実が赤いルビータイプ)、すいかなど
イミダゾールジペプチド
最近注目されるようになったイミダゾールジペプチドは、非常に高い抗酸化作用をもつアミノ酸で、疲労回復物質のFRの生成を助ける働きがあります。疲労回復効果はビタミンCより高いといわれています。
<イミダゾールジペプチドを含む食べ物>
鶏の胸肉、豚ロース、かつお、まぐろなど
分岐鎖アミノ酸
バリン、ロイシン、イソロイシンなど3つの主アミノ酸が含まれており、これが筋肉を構成するたんぱく質を修復する働きをもっています。
<分岐鎖アミノ酸を含む食べ物>
肉・魚・乳製品・卵など
コエンザイムQ10
細胞のエネルギー生成の手助けとなる成分。サプリメントが有名なために摂取は比較的容易なのがメリットとなります。慢性疲労解消群の治療にも効果的という報告もあり、昨今、さらに注目されてきています。
<コエンザイムQ10を含む食べ物>
肉・魚・野菜・卵など様々な食品から摂取可能
フルスルチアミン
高吸収型のビタミンB1となっています。細胞がエネルギーを作る手助けを行っており、脳の働きを活発にする効果もあると言われています。通常のビタミンB1と比べて吸収しやすいといった特徴を持っています。
<フルスルチアミンを含む食べ物>
アリナミンなどに配合されている
クエン酸
細胞のエネルギー生成を手助けする成分となっており、昔から疲労回復に効果的と言われている。尚、クエン酸は疲労予防にも効果があると言われており、クエン酸を含む黒酢を1日1杯飲むだけでも疲れにくい体を作ることができます。
<クエン酸を含む食べ物>
レモン・梅干し・お酢
調理法に注意したい疲労回復の食べ物

疲労回復効果があるといわれる食品でも、調理法によっては効果が得られない場合があります。次のような食べ物は注意が必要です。
豚肉
豚肉に含まれるビタミンB1は「疲労回復のビタミン」といわれますが、豚肉だけ食べるのでは疲労回復効果を十分に得ることができません。ビタミンB1を効率よく摂取するためには、クエン酸を一緒に摂ることが大事です。
クエン酸はレモン、パイナップル、みかん、キウイ、梅、お酢などに多く含まれています。とんかつにレモンを添えたり、豚肉料理と酢の物を一緒に食べたりすると、ビタミンB1とクエン酸の相乗効果で疲労回復効果が高まります。
糖質
頭を使ったときは甘いものが欲しくなります。脳のエネルギー源は糖質だけですから、砂糖を使ったお菓子や料理でエネルギーを補給するのは有効ですが、糖質を摂りすぎると体内でタンパク質と結びついて糖化タンパク質になります。糖化タンパク質が体内に蓄積すると老化が促進され、疲れやすい体になってしまいます。脳のエネルギーを補給するためなら、砂糖を使ったものより炭水化物が適しています。
お客様を元気つける疲労回復メニュー

真夏にバテない!食欲不足も解消できるお勧めレシピ!
材料
豚こま肉 150~170g
にんじん 1/2本
玉ねぎ 1/2個
薬味ねぎ お好みで
塩こしょう 少々
ポン酢 お好み
作り方
にんじんと玉ねぎは千切りにします。豚肉はフライパンで痛めて、塩コショウをふっていきます。豚肉の色が変わってきたら、野菜を入れて炒めていきます。
全体的に火が通ったと思ったら、ポン酢を入れて全体的に混ざるようにフライパンを返していきましょう。
お肉には疲労回復に良いとされる、コエンザイムQ10などの成分が含まれているので、真夏の体力不足に陥りやすい時期に大活躍してくれるメニューとなっています。また、ポン酢を使うのが基本ではありますが、ポン酢をお酢に変えてもサッパリ美味しく食べることができます。
ニラとレモンのW疲労回復食材で疲れを吹き飛ばそう!
材料
もも肉 1枚
ぶなしめじ 1袋
ニラ 1袋
醤油、酒、水 各大さじ1
鶏がらスープの素 小さじ1
レモン 1個
黒胡椒 少々
砂糖(ラカント) 小さじ1
片栗粉 小さじ1
作り方
ニラとしめじをお好みサイズにぶつ切りにします。お肉も食べやすいサイズにカットしていきましょう。あとは、すべての食材をフライパンでしっかりと炒めていきます。
ある程度火が通ったら、材料がこげないように注意しながら、醤油、酒、水、鶏がらスープの素を混ぜ合わせてタレを作り、フライパンに投入。ここでじっくりと、材料とタレを混ぜ合わせていきます。
材料とタレが混ざったら、レモンと黒胡椒、砂糖と片栗粉を一つの容器で混ぜ合わせた後、フライパンに入れてとろみをつければ完成となります。
ニラには、疲労回復に良いビタミンが多く含まれていますし、そこにレモンを加えてクエン酸を摂取するという、疲労回復に効く成分をふんだんに摂取できる料理となっています。
1日1杯!疲れ知らずの体を作るフルーツジュース
材料
お酢
フルーツジュース
作り方
こちらのレシピはとってもシンプルです。
1:5の割合でお酢とジュースを混ぜ合わせて、氷を入れて冷やせば完成。
簡単に作れるので1日1杯飲むようにすれば、疲れ知らずの毎日を送ることができるでしょう。
ここで混ぜ合わせるお酢に関しては調理用ではなく、飲むタイプのお酢を使うようにしましょう。それでも、飲みづらいと感じた時は、リンゴ酢を代用するのがお勧めです。お酢には多くのクエン酸が含まれているので、疲労予防も期待できます。
話題の成分をプラスして最強の疲労回復メニューを作ろう!
材料
山芋 170g(皮付き)
アスパラガス 1束
オリーブオイル 大さじ1
ごま油 大さじ1
塩麹 大さじ1
作り方
アスパラと山芋を食べやすいサイズに切っていきます。山芋は皮をむいておきましょう。
フライパンに食材を入れて、オリーブオイルとごま油で味付けをします。なお、はじめにアスパラガスからいれて、しっかりと火を通すのが良いでしょう。
炒めたら最後は塩麹をまんべんなく馴染ませたら完成となります。ごま油が食欲を引き立てるので疲労で食欲がない時にお勧めの一品となっています。
アスパラの旬となる春先であれば、いつもより高い栄養価を摂取することができますし、ここに塩麹が加われば鬼に金棒の疲労回復メニューが誕生です。
まとめ

いかがでしたか?
最近は、サプリメントが多く開発されていることもあって、食材から栄養を摂る機会が少ない人もいるようです。決してサプリメントを否定するわけではありませんが、大地で育った野菜などの方が、栄養価が高いと言えるでしょう。
疲労回復メニューを考案してお店のウリにすることができれば、一気にお客さんも増えることでしょう。また、常連客の獲得に繋がる可能性もあるので、ぜひ新メニュー開発に取り組んでみて下さい。
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。