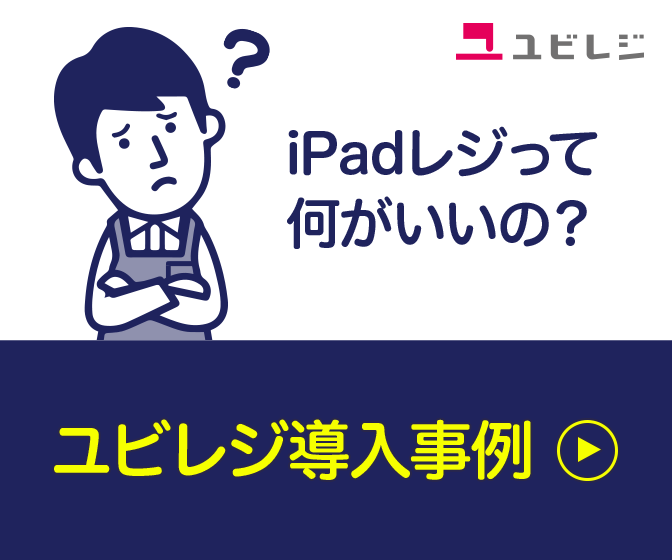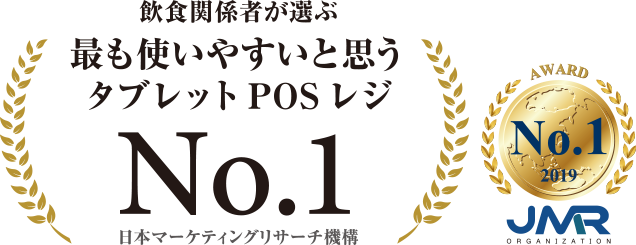寒い冬を超え、徐々に気温が上がり始める春は、入学や入社、転勤、転居などに伴う環境の変化が多い時期です。環境が変わるということは肉体的にも精神的にも大きなストレスとなり、さまざまな心の病を引き起こします。五月の初旬に発症する人が多い五月病も、その1つであるとされます。五月病は、とくに会社に入りたての新入社員なら、だれでもかかる可能性があるといわれています。メンタルヘルスの不調は、放置すると深刻な病に進行してしまう恐れがあります。
病の進行を防ぐためにも五月病に有効なメニューを考え、新社会人を食事の面からサポートしてあげましょう。
五月病とは

新生活のスタートは、やるべきことや覚えるべきことがたくさんあって気持ちが張り詰めているため、ストレスがたまっていても気がつきにくいとされます。
また、忙しさのあまり食事がおろそかになったり睡眠不足になることも多く、体調が悪くなることもあるでしょう。そのような状態でも、新人だから休めないと考えてしまい、無理を押して頑張ろうとします。そのような日々が1か月ほど続いたころに、ゴールデンウィークを迎えることになります。長期休暇であるゴールデンウィークにゆっくり休んで心身をリフレッシュできればいいのですが、根がまじめで仕事熱心な人ほど気分転換ができません。気分転換ができないままゴールデンウィークを終えてしまうと、4月から続く疲れや休みが終わってしまうという辛さによって、これまでピンと張り詰めていた糸が切れてしまったように意欲や気力が低下します。一度張り詰めた糸が切れてしまうと、休みが明けて出社してもミスが多くなったり、イライラしたり、だんだん遅刻が多くなるなど、仕事に身が入らない状態になっていきます。これが五月病の典型的な症状です。
五月病というのは正式な病名ではなく、あくまでも五月に発症しやすいという特徴を捉えた呼称です。精神科や心療内科では、五月病のことを「適応障害」と診断することがあります。適応障害は、就職や失業、昇進、栄転、左遷、離婚、病気などによって環境が大きく変わり、新しい環境にうまく適応できないことがストレスとなって引き起こされる心の病です。ですから、五月病といっても新入社員に限ったことではなく、30代でも50代でも発症のリスクは同じようにありますし、時期も5月だけでなく1年中いつでも起こる可能性があるのです。
五月病にかかわる脳内物質

私たちの心身は、ストレスにどのように反応することで五月病を引き起こすのか、そのメカニズムを簡単に押さえておきましょう。五月病によるメンタルヘルスの不調には、脳内神経伝達物質の「ドパミン」「ノルアドレナリン」「セロトニン」の3種類が深くかかわっていると考えられています。
- ドパミン
ノルアドレナリンが生成される前段階の物質です。快感や意欲、学習、運動、性機能などにかかかわることから、別名「快感ホルモン」とも呼ばれています。不規則な生活などでストレスがたまるとドパミンの分泌が低下し、無気力、集中力の欠如、記憶力の低下などをきたし、喜びが感じられないといった精神症状も起こりやすくなります。 - ノルアドレナリン
ドパミンと同じように、意欲や感情にかかわる物質です。苦しみや悲しみなどの精神的ストレスだけでなく、暑さや寒さ、痛み、疲労などの肉体的ストレスにも反応します。過剰に分泌されるとイライラしたり、キレやすくなることから「ストレスホルモン」「怒りのホルモン」と呼ばれています。反対に、ノルアドレナリンの分泌が減少すると意欲が低下し、物事に対する興味・関心が薄れるなどの抑うつ症状が起こりやすくなります。 - セロトニン
「幸せホルモン」とも呼ばれており、気分や感情、精神の安定などに深くかかわっています。セロトニンには、ドパミンやノルアドレナリンの分泌をコントロールして、ポジティブで安定した精神状態を保つ働きがあります。しかし、強いストレスにさらされるとセロトニン自体の分泌が減少してしまいます。そうなると思考もネガティブになり、意欲も失われてうつ状態に陥ってしまうことがあります。
このように、3つの神経伝達物質は相互に影響し合っています。そのなかの一つであるセロトニンが正常に機能することによって、ドパミンとノルアドレナリンの働きも安定し、仕事にも遊びにも意欲的に取り組むことができるようになるのです。
幸せホルモンのセロトニンを減少させないためには、スポーツや趣味など、心から楽しいと思えることに没頭する時間をもつことと、セロトニンを増やす栄養素を摂ることです。次項では、セロトニンを増やす効果のある食事について見ていきましょう。
五月病に効く食材

セロトニンは、必須アミノ酸のトリプトファンを原料にして生成されます。必須アミノ酸は体内で合成されないため、食品やサプリメントから摂取しなければならないアミノ酸であり、全部で9種類あります。トリプトファンはそのうちの1つのアミノ酸であり、次のような食品に多く含まれています。
- 大豆、大豆製品(豆腐・納豆・味噌・きなこ・豆乳など)
- 牛乳、乳製品(チーズ・ヨーグルトなど)
- 鶏卵
- 魚卵(たらこ、すじこなど)
- 魚類(いわし、かつお、かつお節、さけ、まぐろ、ぶりなど)
- 肉類(鶏、鶏レバー、牛肉・牛レバー、豚肉・豚レバーなど)
- 野菜(ブロッコリー、にら、ほうれん草、枝豆など)
- 果物(バナナ、アボカド、キウイフルーツなど)
- ナッツ類(アーモンド、ピーナッツ、クルミ、ゴマなど)
セロトニンの生成にはトリプトファンだけでなく、ビタミンB6やナイアシン、マグネシウムなどの栄養素も必要です。
- ビタミンB6を含む食品……にんにく、レバー、赤身の魚、バナナなど
- ナイアシンを含む食品……レバー、きのこ、魚類、肉類など
- マグネシウムを含む食品……大豆製品、魚介類、肉類など
レバーや魚類、バナナにはこれらの栄養素が重複して含まれていますから、効率よくセロトニンを増やすことができます。ただし、同じ食材に偏るとほかの大事な栄養素が不足して、結局栄養バランスを崩すことになるので、できるだけ多種類の食材を用いることが大切です。
五月病を乗り切るメニュー

五月病のようなメンタルヘルスの不調には、地中海料理が最適です。地中海料理は豆類やきのこ類、魚介類、ナッツ類を用いるメニューが多く、メインに使う油がオリーブオイルであることがその理由です。
和食の伝統的な献立である「一汁三菜」も、地中海料理と同様の効果が期待できます。ただ、和食の場合は乳製品が不足して塩分が多くなりがちなので、それを意識したメニューを考える必要があります。
地中海料理や和食は、五月病だけでなく生活習慣病などの予防・改善の観点からも世界的に注目されています。こうしたメニューを用意して、新しい生活に踏み出したフレッシュマンを応援してあげましょう。
まとめ

いかがでしょうか?
セロトニンは、睡眠ホルモンといわれる「メラトニン」の生成にもかかわる物質です。トリプトファンからセロトニンが生成されて、そのセロトニンが変化してメラトニンが生成されるという関係です。五月病に悩む新人から、新生活の忙しさに伴う寝不足で悩んでいる新人たちまで、セロトニンアップ効果のあるメニューで新しい生活に踏み出したフレッシュマンをサポートしてあげたいものです。
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。