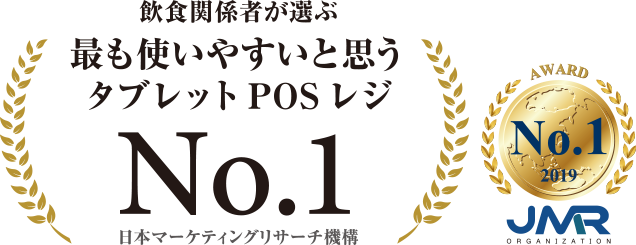飲食業界が未経験でも、カフェは開業できます。ただし、食品衛生・防災系の資格取得、各種の届け出など、開業に至るまでには色々なハードルがあります。全体の流れが把握できないと、スムーズな開業は難しいでしょう。
そこで本記事では、カフェの開業に必要なものを網羅的に解説します。設備や備品の購入、資格の取得方法、届け出の種類、資金調達などを順に説明するので、カフェ開業を考えている方はぜひご確認ください。
カフェを開業するのに必要なもの【設備編】
まずはカフェ開業に必要な店舗設備・厨房機器などをご紹介します。なお、食品営業許可を取るための設備要件があるので、購入時はご注意ください。
シンク(流し台)
シンクの基準として、設置数や大きさが規定されています。具体的には1つの店舗につき2槽以上が必要で、東京都の場合、1つあたりのサイズは幅45cm以上、奥行き36cm以上、深さ18cm以上 が条件です。
手洗い場
シンクとは別に従業員が手を洗う設備が必須です。東京都では、幅36cm、奥行き28cm以上と定められており、手指を殺菌消毒できる装置も併設しなければいけません。特に居抜き物件の 場合、手洗い場が撤去されていることがあるので注意しましょう。
給湯器
飲食店開業では、お湯の出る給湯器を設置する必要があります。単位時間あたりに出せるお湯の量(号数)については、カフェの場合、28号や32号といった大きなサイズが一般的です。
冷蔵庫・冷凍庫
冷蔵庫・冷凍庫を選ぶ基準は、サイズと温度計の有無です。サイズに関して、保管する食材の量に合った 大きさにすることで、電気代の節約になります。また、温度計は保健所が設置を義務付けているため、冷蔵庫本体に付随したタイプか、外付けタイプの温度計が必要です。
製氷機
ドリンクメニュー中心のカフェでは大量の氷を使うため、製氷機を設置すると安心です。氷は冷凍庫でも作れますが、不足するリスクが高いからです。氷の使用量や席数などに応じて、製氷機を選びましょう。
ガステーブル
ガステーブル購入時のチェックポイントは、製品が使えるガスの種類、火力、コンロの口数です。ガスの種類については、事前に物件のガスが都市ガス・LPガスのどちらなのか確認しましょう。火力と口数は、提供メニューと品数を考慮して決定します。
食器棚
飲食店営業許可のために、扉や引き戸のついた食器棚を1台以上設置する必要があります。衛生的な観点で、食器にほこりがつくのを防ぐため です。なお、戸のない食器棚の設置が 認められるケースもありますが、それはあくまで一時保管棚としてなので、本来の基準を満たした状態とは言えません。
テーブル・椅子
テーブルや椅子の選定では、カフェのコンセプト作りにマッチするかが重要です。サイズ、デザイン、材質で店内の雰囲気が変わるので、ターゲット層や理想の回転率を考慮して選ぶのが大切です。
カウンター
カウンター選びでは高さに注目しましょう。スタッフの作業台との高低差によって、お客様からの印象が変わるためです。例えば1mほどのハイカウンターならスタッフの手元が見えず非日常感が演出でき、70cmほどのローカウンターなら調理風景を楽しめます。
照明
東京都では50ルクス以上の明るさが基準ですが、全国共通の規定はありません。お店のコンセプトに沿って、明るさの強弱、自然光の有無、照明を設置する位置などを決めましょう。
音響
カフェの 音響設備には、「天井埋め込み型」、「据え置き型」、「ペンダント型」の3種類があります。スピーカーを見えないようにするのか、あえてインテリアとして活用するのか、お店の雰囲気に合わせて判断します。
カフェを開業するのに必要なもの【備品編】
次にカフェの開業で必要な備品と、購入時の注意点を解説します。
カップ・グラス
提供する飲み物に応じて用意する器は異なります。店舗の雰囲気やインテリアに合わせるのも良いでしょう。器は飲み物の味と同じように顧客の印象に影響するので、じっくり選ぶことをおすすめします。
【関連記事】
コーヒーカップの大きさ、かたち、どれを選べばいいの?
コーヒーマシン
ハンドドリップ式で抽出しない場合はマシンを用意しましょう。ボタンを押せば簡単にコーヒーが淹れられます。ただ、高価なものが多く、買い替えは容易ではないので慎重に選びましょう。
【関連記事】
カフェでおすすめのコーヒーマシンやその選び方とは?
テーブルに置く備品
メニューブック、メニュースタンド、コースターを選ぶ際は、素材や柄を意識しましょう。機能性や雰囲気は商品によってさまざまです。
調理器具
提供メニューに応じて、包丁、まな板、フライパンなどを購入しましょう。低価格のものを選んで節約するのも良いですが、最低限の使い勝手と耐久性は重要です。
会計備品
手動で会計するには、クリップボード、伝票立て、キャッシュトレイなどが必要です。タブレット会計に馴染みのない客層なら、購入を検討しても良いでしょう。
レジ用品
客層やお店の規模に応じて、レジ用品を購入しましょう。個人カフェは手動会計で十分なこともあります。一方、フランチャイズならば、POSレジの導入で複数店舗の一元管理をするのが便利です。
【関連記事】
POSレジとは?(POSシステム)
カフェの開業に必要な資格・届け出とその取得方法

<カフェの開業に必要な資格>
|
必要な資格・届け出 |
取得方法 |
|
飲食店営業許可 |
店舗が完成する10日前までに、管轄の保健所に申請を行う。 必要書類:営業許可申請書、店やキッチンの間取り図、資格証明書、申請料(約1万円ほど)。 ※取得した営業許可証は店内の目につきやすいところに掲示しましょう。 |
|
防火管理者選任届 |
防火管理者の有資格者でも、店舗の開業日までに管轄の消防署に防火管理者選任届を届け出る必要がある。(この申請を行う必要があるのは、収容人数が30人を超える店舗のみ)。 |
|
防火対象物使用開始届 |
店舗の規模などで申請の要、不要が変わってくるため、管轄の消防署に問い合わせが必要。もし必要な場合、開業の7日前までに、防火対象物使用開始届出書、店舗近辺の地図、消防用設備が記入された店舗の平面図・立体図・断面図、建物の仕上げ表などを揃え、届け出る。内装を業者に頼んでいる場合は、内装業者が代行可能かも要確認。 |
|
火を使用する設備等の設置届 |
火を使用する設備を設置する場合に必要な届け出。IHではなく火でお湯などを沸かす場合は、届け出が必要。1つのキッチンで使用する設備の電力合計が350キロワット以上となる場合、届け出なければならない。開業するカフェがこれに該当するかどうか分からなければ、その厨房設備を導入した業者などに確認し、必要であれば設備設置前までに届け出なければならない。 |
|
個人事業の開廃業等届出書 |
確定申告をする上で絶対に必要な届け出。個人で開業する場合は、開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署に届け出る。 |
|
労災保険の加入手続き |
正社員、アルバイト問わず従業員を雇う場合、労災保険に加入する必要がある。これは雇用した日の翌日から10日以内に、管轄の労働基準監督署に届け出る。 |
|
雇用保険の加入手続き |
従業員を雇う場合、雇用保険にも加入する必要がある。ただし、それがアルバイトやパートなどの場合、以下の2つを満たした時のみに必要となる。 ・契約している内容として、1週間の労働時間が20時間以上であること ・31日以上継続して雇用される見込みがあること 上記2つに当てはまる場合は、雇用日の翌日から10日以内に公共職業安定所に届け出なければならない。 |
|
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 |
昼間にワインやビールを出すだけであれば必要ないが、深夜12時以降にもアルコール類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を管轄の警察署に、営業開始の10日前までに届け出る必要がある。 カフェですから基本的にはないが、スタッフがお客様の隣に座って水割りを作るなど接待行為を行う場合は、「風俗営業許可」が必要となる。その場合は、営業開始の約2ヶ月前までに届け出る。 |
カフェ等でケーキやパンをテイクアウトで販売する場合は、「菓子製造業」の許可も必要になります。 防火管理者の資格は収容人数や延べ面積によって資格区分が異なるため、地域の消防署などに電話などで問い合わせをしましょう。開業届けについてはこちらも参照してください。
お店を開くのに必要な開業届 | 手続きの方法からスケジュールまで徹底解説
カフェ開業に必要な資格の取得方法
食品衛生管理者
食品衛生責任者とは、営業者の指示にしたがって、ある施設や部門において食品衛生の管理を担当する人のことです。本資格は、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学などについて一定の知見を有することの証明になります。現場での役割は、食品衛生を保つための手順書の作成、衛生管理の実施状況の記録、スタッフへの衛生教育などが挙げられます。
防災管理者
防火管理者とは、多くの人が利用する施設・建物などの火災の被害を防ぐために、防火管理業務を行う人のことです。本資格は、防火管理業務に必要な知識・スキルを有する証明になるため、消防計画の作成などを担えるようになります。
一般財団法人日本防火・防災協会 https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html
カフェ開業の際に持っていると便利な資格と取得方法

小さなカフェといえども「経営」をし、毎年確定申告をしなければなりません。法律上特に必要ではありませんが、確定申告を毎年行わなければならないことを考慮に入れると、簿記など役立つ資格も可能であれば取得したほうが良いでしょう。
|
資格 |
メリット |
|
日商簿記3級 |
・簿記3級は商業高校卒業レベルでありながら、取得すれば簿記の基礎が身につく |
|
調理師免許 |
・調理に関する専門知識をひと通りマスターできる ・調理師免許を持っていることを来店客に示し、信頼感が得られる ・仮に、どこかの飲食店に調理人として就職することを考えた場合、有利となる |
カフェ開業を円滑に行える資格
日商簿記3級
「簿記」とは、毎日の売上、仕入れ、支払いなどを「複式簿記」のルールで分類し、記録していく金銭管理の手法です。簿記には、複式簿記と家計簿のようなイメージの単式簿記がありますが、税金を納める上で優遇される「青色申告」をするためには、複式簿記で金銭管理をする必要があります。そのため、複式簿記のやり方を知っておくほうが良いでしょう。簿記には1級から4級まであります。カフェ経営には、簿記の基礎を習得できる3級の取得が最も適切でしょう。「日商」というのは、簿記の資格を認定している3つの組織の1つで「日本商工会議所」の略です。ほかの団体主催の簿記資格でもかまいませんが、日本ではこれが1番メジャーとされています。ただし、この簿記3級を取得するには試験に合格する必要があります。この試験は年に3回行われており、受験資格は特にありません。合格率は直近で56.1%となっているため、取得を希望する場合はしっかりと勉強して試験に臨みましょう。独学で勉強するのには限界があると感じる人は、簿記の専門学校に通うことも検討しましょう。専門学校に週1回、3ヶ月程度通えば合格ラインに達することができるかもしれません。通学する以外にも、簿記の通信講座も多数ありますので、こちらも検討ください。お金の管理が苦手な方も少なくないと思いますが、毎日の売上や人件費や食材費など経費関連含めたお金の動きをリアルタイムで把握できるようにしておくことで、どの経費を削減し、どこを改善すべきかがわかり、迅速に対応することも可能になり、店舗にとってもプラスになります。
提供するメニューの幅を広げられる仕事
調理師免許
料理の基礎を心得ていたほうが、こだわりを感じられるよりレベルの高いメニューを提供できます。一般的なメニューよりもひと工夫したメニューを提供した方がお店の差別化にもなります。カフェの開業に関しては法律で取得が定められた料理に関する資格はありませんので、カフェ専門の料理学校などに通っても良いですし、以下で説明する調理師免許を取得するのでも良いでしょう。
調理師免許の取得方法には、2つのルートがあります。1つは厚生労働大臣が指定した調理師学校に入学し、1年~2年の授業を受けて卒業すること。もう1つは、2年以上飲食店における調理の実務を経験したうえで、調理師試験を受験することです。カフェを経営しながら取得を目指すのであれば、2番目が現実的でしょう。試験を受けた場合の合格率は、直近で61.6%となっています。受験すれば誰もが合格できるわけではないので、しっかりとした準備を持って試験に臨みましょう。
コーヒーを提供するときにあると良い資格
カフェを開業するために、コーヒーの専門の資格は特に必要ありません。しかし、コーヒーに関する資格がある、もしくはコーヒーに関する認定を受けているお店であるなら、他のカフェと差をつけられ、かなりの強みになるでしょう。最近ではコーヒー好きが高じて、お客様の中でもコーヒーの淹れ方やコーヒー豆に関する知識がある人も増えています。カフェに行くならコーヒーの専門家がいるお店でコーヒーを楽しみたい、専門家からアドバイスをもらいながらコーヒー豆を選びたい・購入したいという方も少なくありません。店舗内で定期的に淹れ方のコツなどをレクチャーするコーヒーセミナーなどを開くとお客様にも喜ばれリピート顧客獲得もできるかもしれませんね。
コーヒーマイスター
コーヒーマイスターとはコーヒーに対する深い知識と基本的な技術を修得し、認定試験を受けて資格を取ることを指します。日本でもこの資格がある人はそれほど多くありません。
しかし、注意点として、日本スペシャルティコーヒー協会の会員にならなければこの試験をうけられません。しかも会員になるには個人または企業として会員になる必要があります。もし個人で会員になる場合、およそ1~3万円ほど必要になります。
民間団体のカフェ開業コース
民間団体が主催するカフェ開業コースなので費用の面での負担が少なく、コーヒーの知識やコーヒーの抽出技術なども学べます。特にメリットなのが、カフェの開業を重視したコースのため、開業に向けてのノウハウやサポートも受けられます。お店の利益を出す方法や仕入れ方法、コーヒーの焙煎、料理のメニューについてなどどれも役立つものばかりなので、カフェ開業前に受講を検討できます。
JBA認定 バリスタライセンス
専門学校で採用されているバリスタ資格です。主にエスプレッソマシンの使い方などを学ぶため、ドリップの入れ方を極めたい人にはあまり向いていません。またこの資格試験を受けるには、JBA認定のカリキュラムを受けた人、またはカフェで一年以上働いた経験が必要です。
コーヒー鑑定士
「商品設計」、「生豆鑑定」、「品質管理」の3つの教科を合格する必要があります。受験料も他の資格と比べると高額で、コーヒー関連の資格の中でも合格難易度が高めの資格です。
他にもQグレーダーなどの資格もあります。詳しく情報はこちらのサイトを参照してください。
一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会 https://scaj.org/
お酒を提供するときに必要な資格
もしカフェでお酒も提供したいと考えている場合、お酒に関する知識があるなら安心して、お酒を提供できます。またお客様に、よりおいしいお酒を提供できるでしょう。最近ではカフェでノンアルコール飲料だけでなく、アルコール飲料を提供しているお店も増えてきています。お店の雰囲気やコンセプトにぴったりのアルコール飲料を研究して、可能ならそれに関する資格を身につけておきたいですね。
ソムリエ
お酒の資格と聞いてすぐに思い浮かぶ資格はソムリエではないでしょうか。試験内容としては、ワインに対する全般知識と実技試験があります。実際ソムリエ試験の合格率は低いので資格を取得するにはかなり大変ですが、もしこの資格があればとても重宝されます。さらに実技試験のないワインエキスパートという資格もあります。また、これよりも簡単に入手できる資格としては、ウイスキー検定があります。
ビアテイスター
日本地ビール協会が実施しているクラフトビールの資格です。これは一日で取得可能な資格です。お店でクラフトビールを提供しているなら、この資格があると有利かもしれません。
バーテンダー
日本ではバーテンダーの資格がなくても、バーテンダーの仕事ができます。しかしこの資格は実務経験が必須です。そのためカフェを開業するにはすぐにこの資格を使用して仕事をすることは難しいかもしれません。しかし、もし経営者がバーテンダーの資格を有していれば、カフェでも他のお店と確実に差をつけられるでしょう。
カクテル検定
これは日本カクテル文化振興会が実施している検定です。筆記のみの試験のため、割と簡単に取得できる資格といえるでしょう。カフェでアルコールを提供する場合、カクテルを扱うお店も多いようです。カクテルは若い女性に人気なアルコール飲料なので、できればこの資格を取得して、オリジナルカクテルを提供してみたいですね。
テキーラマエストロ
カクテル関係で最近人気が出ている資格です。テキーラに関する全般知識やテイスティングについて学習できます。また一日で取得できる資格なので、カフェを開業する前にこの資格を取得しておくこともできるでしょう。幅広いアルコール飲料を提供できると思います。
差別化やサービス品質の向上に繋がる資格
開業に必須の資格ではありませんが、有資格者がいることでお店のアピールやサービスの向上につながる資格をご紹介します。
野菜ソムリエ
野菜ソムリエは、一般社団法人日本野菜ソムリエ協会の認定資格で、資格自体は「野菜ソムリエ」「野菜ソムリエプロ」「野菜ソムリエ上級プロ」と3種類あります。3種類の野菜ソムリエの資格は、目的や用途に応じて取得することができます。
フードコーディネーター
日本フードコーディネーター協会が認定している資格です。食品メーカーの商品開発など、レストラン、料理教室プロデュース、メニュー開発、雑誌など写真スタイリング、イベント運営、メディア企画など、フードビジネスに関連する仕事で活躍できるの食のクリエーターとして位置付けられています。
製菓衛生師
都道府県知事が行う製菓衛生師試験の合格者に対して、各都道府県知事が付与する国家資格です。
洋菓子・和菓子などジャンルは問わず、菓子づくりに関する知識や技術、添加物やアレルギーなどの食の安全に関わる部分の知識が身についているという証明になります。
カフェの開業準備に関するよくある質問
最後に、カフェの開業準備で頻出する質問に回答します。
開業の準備を始める前にしておいたほうが良いことはありますか?
開業するカフェのコンセプトを考えておくことをおすすめします。お店の方針が定まることで、競合店との差別化を図りやすくなり、事業計画の立案にも活用できるからです。コンセプトは設備や備品選びの基準にもなるので、早い段階で明確にしましょう。
【関連記事】
カフェ開業時に決めたいコンセプトの重要性や考え方、注意点
カフェ開業資金はどれくらいかかりますか?
どのようなカフェを開業するかで変動しますが、およそ1,000万円~2,000万円です。開業資金の内訳は店舗の取得費、設備の工事費、内装工事費、備品や消耗品の購入費、チラシなどの広告宣伝費、開業後に経営が軌道に乗るまでのランニングコスト(例:家賃)などがあります。
これらを自己資金だけで賄うのは難しいので、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の活用や金融機関からの借り入れを検討しましょう。
【関連記事】
カフェ開業に必要な資金の目安や内訳は?調達方法や節約するコツ
カフェの開業にはさまざまな下準備が必要

カフェの開業では、さまざまな準備を計画的に進めていくことが大切です。例えば、設備や備品の購入では、事前にお店のコンセプトが明確になっている必要がありますし、食品営業許可の取得には保健所への相談が必須です。また、そもそも購入費を賄うには金融機関からの融資が欠かせず、そのためには事業計画書を用意しなければなりません。
カフェの経営を成功させるためにも、本記事でご紹介した項目を参考にしてみてください。
【開業に関するおすすめ記事】
▽開業資金について、資金調達の方法や開業後の運転資金などを確認しておきましょう!
飲食店開業資金の目安は?内訳や調達方法、コストを抑えるコツ
▽開業資金の目安、必要な開業資金の目安は?自己資金で足りない場合はどうしたらいい?物件取得費や宣伝費など内訳もチェック!
開業資金に必要な額と内訳|事業を始めるための資本金を調達する方法
▽開業スケジュールや立地選びのポイント、家賃の目安などを紹介
https://recipe-book.ubiregi.jp/articles/cafe-kaigyou-old-apanese-style-house/
▽フランチャイズに加盟して開業する方法をご紹介
憧れのカフェはフランチャイズで叶えられる?
▽近年、再注目されているキッチンカーでの開業について
キッチンカー(移動販売)で開業メリット・デメリット、開業資金相場とは?
▽居抜き物件を選ぶ際のポイントや注意点をご紹介します
飲食店の居抜き物件のチェックポイントや探し方
▽中古の厨房機器購入で開店資金を節約!
中古厨房機器で開店資金を節約しよう!
▽お店のコンセプト作りから取りかかろう
飲食店・店舗のコンセプトの作り方・考え方
▽焼肉店開業に融資を受けるためには?!
焼肉店を開業する時に融資を受けるためにすること
▽用意すべき調理機器や食器の数を把握しておこう!
飲食店開業時の備品リストは?準備しておくべき備品一覧
▽Wi-Fi導入のメリットとデメリットとは?
飲食店にWi-Fiを設置することのメリットとデメリットとは?選ぶ基準や設置法、設置事例もご紹介します!
▽創業計画書の作り方について解説します。
創業計画書の書き方!日本政策金融公庫の融資審査を高確率で通す方法
▽SNSを使った集客の方法をご紹介!
飲食店が集客増するためのSNSマーケティング戦略とは | Twitter、Facebook、Instagram、LINEの活用法
▽ラーメン屋開業へ向けて必要な資金や準備について解説します!
ラーメン屋開業に必要なことを確認!失敗しない店作りを目指そう
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。