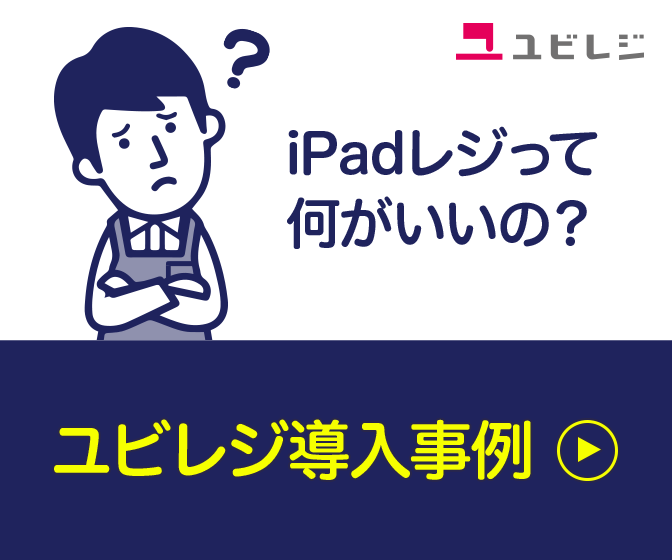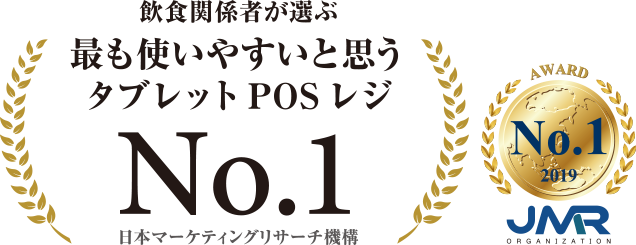飲食店におけるビールの提供方法は、大きくわけて2つです。1つは、瓶ビールにグラスを添えて提供するスタイル。もう1つが、瓶ビールではなく樽から直接ビールを注ぐ、いわゆる「生ビール」のスタイルです。後者をしようとした場合、ビール樽を持ち上げてグラスに注ぐわけにはいきませんので、ビールサーバーが必要となります。
ビールサーバーは、購入するだけではなくレンタルもできます。業界としては、むしろレンタルの方が主流です。そこで今回は、ビールサーバーとは何かということから、ビールサーバーをレンタルした場合のメリットとデメリット、そして導入方法に至るまでご紹介いたします。
ビールサーバーとは

ビールサーバーとは、具体的にどういう器具なのか詳しくご紹介いたします。
ビールサーバーの定義とは
ビールサーバーの定義は、「ビールをグラスやジョッキに注ぐ器具」です。具体的な構造は、ビールの入っている樽などの容器に炭酸ガスを送り込み、その圧力で中のビールを押し出すものです。導入しているのは主に飲食店が多いですが、最近では自宅でも本格的な味わいやクリーミーな泡を簡単・手軽に楽しめるような家庭用のものも販売されています。缶ビール専用、瓶ビールの電源不要で屋外でも気軽に使えるミニサイズのものから、キリンから発売されている家庭用のものなどがあります。
【参考】家庭用ビールサーバー
キリンホームタップ / キリンビール株式会社
ビールサーバーの種類
ビールサーバーには、構造として2つの種類があります。
1つは、「樽冷式サーバー」です。これは、ビール樽を入れて置く部分そのものが冷蔵庫になっているので、樽自体を冷やして冷たいビールを出すものです。
樽自体を常に冷やしておけるので、いつも冷たいビールを提供できると同時に、樽に入っているビールの品質を常に維持することができます。しかし、ビールサーバーのサイズが大きくなってしまうことが一番の懸念点です。なぜなら、樽冷式サーバーの場合、予備の樽も冷やしておかないといけませんから、冷蔵庫部分は樽が2つ入る広さになります。したがって、本体自体も非常に大きくなり、場所をとってしまうのです。ただでさえ狭いところにいろいろな器具を詰め込む飲食店のキッチンやデシャップでは、この場所を確保するのはなかなか大変でしょう。
2つめは、「瞬冷式サーバー」です。これは、サーバー内に冷却用の氷を常時作って氷水を溜めておく水槽があり、その水槽の中にビールの通る管が配置されている仕組みになっています。ビールは、樽から出てグラスに注がれるまでに氷水の中の管を通ることで瞬間的に冷却され、冷えたビールとして注がれるのです。
瞬冷式サーバーは、平均して縦横30cm×高さ50cm程度の大きさでコンパクトです。サーバーから直接グラスにも注げますし、よくバーのカウンターにある「ドラフトタワー」につなぎ、そこからグラスにビールを注ぐこともできます。ただし、ビールのオーダーが頻繁に入ってしまうと冷やすことが間に合わず、キンキンに冷えた状態ではないビールを提供することになってしまいます。デメリットはあるものの、省スペースというメリットは捨てきれないため、ほとんどの飲食店はこの「瞬冷式サーバー」を設置しています。レンタルされるのもこちらのタイプです。
ビールサーバーを使用するメリットとデメリット

両方のビールサーバーに共通しているメリットとデメリットは、以下の通りです。
メリット
- 炭酸ガスの圧力によって空気が入らないため、ビールの量が減っても「気」が抜けない
- ビールに触れている気体は炭酸ガスなので、樽内部のビールが酸化せず、品質が維持できる
- 常に冷たいビールが提供できる
- 樽詰めのビールの方が瓶ビールより一般的に言って品質が高い
デメリット
- 瓶ビールだけを提供するのに比べて、ビールサーバー自体とビール樽をストックする場所が必要になる
- ビールの発注単位が最低15リットルなので、あまりビールの注文がない店の場合は在庫効率が悪い
【関連記事】
ビールの注ぎ方にこだわって美味しいビールを提供しよう!
ビールサーバーから入れるものが「生ビール」ではない

ビールサーバーの概要とメリット、デメリットが分かったところで、ビールサーバーをレンタルで導入する場合について触れていきます。しかしその前に、飲食店の人でさえ勘違いしがちな誤解を1つ解いておきます。それは、「生ビール」についてです。
生ビールとは何か
飲食店でよく使われる「生ビール」とは、一体どのようなものかご存知でしょうか。実は、ビールは製造最終工程で、発酵を止め品質を維持させるために熱処理を行う種類のものと、その工程のないものがあります。前者が「ラガービール」、後者が「生ビール」です。よって、「ラガービールで生ビール」というものは存在しません。
日本のメジャーなビールで言えば、キリンラガーはその名の通りラガービール、スーパードライやキリン一番搾りは生ビールです。つまり、スーパードライが瓶に入っている状態で提供されたとしても、それは「生ビール」なのです。
しかし、ビールサーバーから提供するものを「生ビール」だと勘違いされている方も少なくありません。メニューにも、「瓶ビール」と「生ビール」という括りで書いているお店がほとんどです。厳密な意味で考えるなら、その2つは「同じもの」であることが多いのです。その証拠に、瓶のスーパードライのラベルにも大きく「生」と書いてありますので、1度確認してみてください。ビール工場でも、同じ製造工程でできたビールを瓶にも樽にも充填します。ちなみに、市販で販売されている缶ビールにも、よく見ると「生ビール」と表記されているものがあります。2021年4月に発売され人気となった『アサヒスーパードライ生ジョッキ缶』も生ビールです。
なぜいわゆる「生ビール」の方がおいしいか
では、なぜ「生ビール」の方がおいしいのでしょうか。その理由は、「保存状態」による「品質維持」の問題があるからです。
瓶ビールは、一般的に配達の際にトラックの荷台に載せられ、場合によっては遮光のカバーもかけられずに運搬されています。したがって、その間に温度や日光の影響を受け、品質が劣化してしまう危険性が高いのです。これに対し、樽のビールはその容器の性質上、遮光性は完璧です。温度も外気の影響を受けにくくなっています。したがって、製造直後のビールの品質を維持しやすいのです。
つまり、いわゆる「生ビール」の方が「できたて」に近い味のため美味しいわけです。たとえば、ビール工場で瓶詰めしたばかりの瓶ビールを飲んでみると、味は樽生と全く同じだと感じるはずです。
つまり、「ビールサーバーを導入する」=「生ビールを提供できるようになる」ということではないのです。
ビールサーバーの導入方法

生ビールについての誤解を解いたところで、いよいよビールサーバー導入の話です。導入の方法には、レンタルと購入があります。レンタルの場合、費用はどの程度かかるのでしょうか。
レンタルについて
ビール樽購入とセットで「無料」
ほとんどの場合、ビールサーバーのレンタル料は「無料」です。では、レンタル元である酒店やビールメーカーは、どこで儲けるのでしょうか。それは、レンタルとビール樽でのビール購入をセットにすることで、売上を稼いでいるのです。つまり、ビールを樽で購入すればビールサーバーは料金は無料で貸し出してくれるのです。
酒店から購入する場合は、樽1個を購入すれば、その樽の中にビールがある間、あるいは決められたある程度の期間内は、ビールサーバーを無料でレンタルできる方式がほとんどです。サーバー設置のエリアは酒店の配達エリアに限られる場合がほとんどですので注意してください。(配送料がかかる場合もあります)
メーカーとビール専売契約を結んで「無料」
ビール樽とセットではなくても、実質的にセットであればビールサーバーを無料でレンタルしてくれます。
つまり、決まったビールメーカーと「ビールはそこの会社の製品しか扱わない」という専売契約を結んだ場合には、ビールサーバーを契約期間中ずっとレンタルしてくれるのです。
イベント時などの一時的なレンタルも可能
例えばパーティーや地域のお祭りや野外のイベント会場などの出店時、キャンプやバーキューなどのアウトドア向けにビールサーバーのレンタルサービスを行なっているメーカーや酒店もあります。基本的に当日利用はできず、事前に予約が必要です。利用日を伝え、貸し出しや返却の方法もあわせて早めに相談してください。
購入について
酒屋やメーカーに縛られず、自分の気に入った銘柄のビールを提供しようと思った場合、ビールサーバーは購入になります。この場合、「瞬冷式サーバー」タイプの中古で価格は5万円前後、新品の場合は20万円前後になります。
ただし、炭酸ガスなどの消耗品も購入する必要があります。価格は、炭酸ガスボンベ1本で3万円程度です。
本体だけでなく、ホース付きの減圧弁やコック(注ぎ口の部分)などの部品も中古で販売しており入手可能です。(不要になった際には通常のゴミでは廃棄できない場合があるので、地域のゴミ処理センターなどに電話相談してから廃棄しましょう。)
ビール樽は酒屋で購入できます。来店して直接購入に出向けば送料もかかりません。購入時には保証金込みの値段を支払いますが、空樽の返却時に保証金が返ってくるシステムです。在庫数は酒屋によって違うため、必要な銘柄と容量の在庫用意があるかあらかじめ確認してから購入することをおすすめします。
ビールサーバーをレンタルするメリット・デメリット

ビールサーバーをレンタルするメリットについては前述してきましたが、改めてメリットとデメリットについて整理しておきます。
メリット
- ほとんどの場合無料
- メンテナンス不要(壊れたら酒屋やビールメーカーが無償で修理または交換の対応をしてくれる)
- 炭酸ガスなどの消耗品も無料
- 専売契約をした場合は、ビールの仕入れ高によって協賛金という名前のキックバックや、ドリンクメニューの製作・印刷費を一部負担してくれるなどの販促協力がある場合も
日々のメンテナンス(ガス圧の調整やヘッドの清掃など)や困ったことがあった時にも、メーカーのQ&Aページや、手順をYouTube動画で公開されているものもあるので安心ですね。
デメリット
- 専売契約の場合は、最低1年間はメーカーを変更できない
- 樽で仕入れるので在庫効率が悪い
- 仕入れ価格は相手との力関係次第
ビールサーバーはどこからレンタルするのか

ビールサーバーをレンタルで導入しようと思った場合、どのような方法で酒屋やメーカーにアプローチすればよいのでしょうか。
ネットで探す
ビールサーバーのレンタルは、個々の酒屋、または酒類卸問屋が実施しています。ビール樽を購入したら、ビールサーバーを無料レンタルしてくれるところをネットで個別に探すしかありません。
ビールメーカーに打診する
専売契約をすることも含め、ビールメーカーの営業に問い合わせるのが次善の策です。3大メーカーと言われているビールメーカー窓口のURLをご紹介しておきます。
アサヒ:https://www.asahibeer.co.jp/aboutus/branch/
サントリー(サントリー酒類):https://www.suntory.co.jp/company/branch/office.html
キリン:https://www.kirinholdings.com/jp/profile/organization/kirinbrewery/office/head_office/
上記以外のメーカーでも貸し出しは行なっていますので、インターネットなどで調べてみましょう。
まとめ

いかがでしょうか?
在庫効率が悪くなる点と、ビールサーバーの設置スペースを確保しなければならない点を除けば、いつでも冷たいかつ品質が保たれたビールを提供できるのがビールサーバーです。レンタルであれば投資が不要という点でメリットもあります。ドリンクメニュー商品のパワーアップを考えるのであれば、ぜひビールサーバーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【おすすめ関連記事】
ビールタンブラー次第でビールの味が変わるってホント!?
クラフトビール人気は終わらない?ドリンクでも店の特徴をだそう
【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】
店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。
現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。
「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。
実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。